
第106号/1998.7
■第203回サロン・ド・エナ開催
■理事長退任・就任のご挨拶
■研究企画委員会報告
■センター運営会議報告
■平成10年度の調査研究スタート
■臨時大深度地下利用調査会の最終答申
■会員の皆様へのお知らせ
■渡辺理事長退任・園田新理事長就任■
平成10年7月1日をもって、渡辺英二氏(日揮㈱ 代表取締役会長)が退任され、新しく園田保男氏(東洋エンジニアリング㈱代表取締役社長)が理事長として就任されました。
渡辺理事長には、2年間にわたりご活躍いただき、当センターにもご尽力いただきました。引き続き、園田新理事長より当センターの今後の発展にお力添えいただくこととなります。 (次頁にご挨拶を掲載)

■第203回サロン・ド・エナ開催■
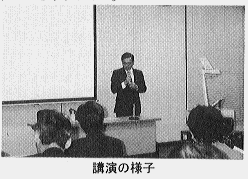
6月17日(水)に第203回サロン・ド・エナが開催されました。今回は、当センターの担当分として、佐藤工業(株)土木本部技術部門部長の桐谷祥治氏をお迎えし、「世界初-超近接回転移行シールドの記録」~自治体が注目~というテーマで、ご講演いただきました。概要は、以下のとおりです。
京都市地下鉄東西線の御陵東工区は、京阪電鉄京津線と地下鉄東西線が乗り入れる区間で方向別2層式ホームへ2線ずつ誘導することから、立体交差型4線移行方式の複雑な地下構造物の建設となりました。開削工法も検討されていましたが、路上の交通が過密状態であることから泥土圧シールド工法を採用し、最近接時のトンネル離隔0.7m(全区間0.5D)という4トンネルの相互影響を避けられない技術難度が高い施工へ挑むこととなりました。世界初の試みに際し、技術検討体制の確立、シールド機の仕様統一、必要な技術開発と施工管理方法等あらゆる検討を行いました。
まず、覆工の設計に当たっては、段階的に施工する4本のシールド掘進による周辺地盤の応力状態、後続シールドの推進による先行トンネルへの影響の評価・検討を行いました。また、高精度かつ滑らかな掘進線形を確保するために掘進位置・姿勢結果に基づきシールドの姿勢を推進距離100mm毎に制御する自動方向制御システムを採用し、さらに、先行トンネル掘進実績を分析して切羽地山を推定、その結果を順次後続シールドヘフィードバックする高精度掘進管理と計測管理を組合せた後続シールドの総合的情報化施工技術を開発しました。本工法は世界で初めて採用し成功させたもので、地上と地下の過密問題に直面している多くの自治体から注目されています。
当日は、多数の方々にご聴講いただき、活気あるサロンとなりました。

■理事長退任・就任のご挨拶■

●退任のご挨拶
平成8年に理事長をお引き受けして2年間がたち、このたび退任することとなりました。この2年間を振り返ってみますと、当初日本経済は長い停滞期を脱して回復に入るかと思われていましたが、昨年に入って消費税の引き上げ・医療費の改定などもあって再び大きく落ち込み、本年6月には東南アジアの経済危機の影響もあり、為替レートは1ドル145円を越えて下落、株価も1万5千円を切るという危機的状況になっています。なにか国全体が自信を失ってしまったかのように見えます。しかし自然現象にも社会現象にも上昇一辺倒とか下降一辺倒ということはありません。かならずどこかに次の発展の芽が頭を出しているはずです。我々はそれがどこにあるかを見出さなければなりません。病は気からと申しますが、景気も気からであると思います。悲観一色になることなく、それぞれの立場で努力を続けてゆこうではありませんか。
地下開発利用研究センターではミニ・ドーム・プロジェクトを無事完成させることができましたが、今後はここで得られた知見を備蓄問題をはじめ、各省庁の枠を超えた地下開発の分野に広げてゆくことが望ましいと考えます。
私の在任中、通商産業省をはじめ尽力をいただきました会員会社、関係諸機関、ならびに協会の事務局の皆様の努力に心から感謝いたします。
●就任のご挨拶
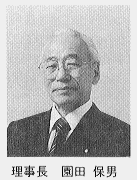
このたび当協会の第9代理事長をお引き受けすることとなりました。協会発展のためにご尽力された歴代の理事長を見習い、甚だ微力乍ら与えられた職務を誠心誠意全うしたいと考えておりますので、通商産業省のご指導とともに会員各社の皆様のご支援・ご協力を切にお願い申し上げる次第でございます。
相対的には地価が高く、地震への備えも不可欠なわが国にとって、地下空間が持っているメリットを有効活用すること、特に大都市の過密を改善するために地下空間を利用することは、バブルの時代ほどではないとは言え今後とも様々な局面で検討されるものと考えられます。本年5月に首相の諮問機関である「臨時大深度地下利用調査会」が大深度地下利用制度の法制化に関する答申を取り纏めたことは、わが国の地下空間利用に対する重要性や更なる可能性を示すものと言えましょう。
1978年8月に設立された当協会は、本年20周年という節目の年を迎えますが、'89年9月当「地下開発利用研究センター」を発足させて以来、地下空間を構築する技術の高度化と地下空間システムのために積極的な役割を果たして参りました。
地下空間を利用するに当たっては、安全性の確保、環境との共生、メンテナンスの容易性など解決すべき事項や技術等が数多く存在します。これまでの大深度地下空間開発技術の実証設備であるミニドームの建設や石油・ガス地下備蓄の調査研究を通じて当センターに蓄積された技術や経験は多大なものとなっており、今後の新しいニーズに対応できる基礎が確立し次のステップに進む準備が整ったものと思われます。
「エンジニアリング」という共通の視点に立って様々な業種の会社が参加されている当協会の特色を生かし、会員各社がこれまで培ってこられた英知の結集により、地下空間利用の分野においての貢献ができれば幸いであります。
今後共、通商産業省をはじめ関係諸機関、当センター会員企業の皆様のご指導を切にお願い申し上げ、就任のご挨拶をさせて頂きます。

■研究企画委員会報告■
平成10年度の第1回研究企画委員会が、6月23日(火)に開催されました。山口専務理事の挨拶の後、新委員の紹介があり、委員長には瓜生喜久雄氏(清水建設㈱ 常務取締役)が昨年度に引き続き就任されました。委員会は、瓜生委員長以下19名の委員で構成されています。委員長の挨拶の後、来賓を代表して通商産業省環境立地局産業施設課の小林課長補佐殿よりご挨拶をいただき、議事の審議が行われました。議事内容は、以下のとおりです。
議題1:平成9年度事業報告および決算報告について
議題2:平成10年度事業について
議題3:平成11年度テーマ募集について
議題4:平成10年度年間活動計画他について
当日の会議は、理事会付議事項としての平成9年度事業報告(案)および決算報告(案)の審議と、平成11年度テーマ募集についての審議ならびに平成10 年度事業内容と年間活動計画(案)の報告が行われ、いずれも承認されました。平成10年度の地下利用推進部会の改編に伴う委員参加募集については、5分野にて募集した結果、59社69名の応募をいただきました。なお、部会編成として、募集時の5分野のうち、都市再構築部会と次世代都市構想部会、新産業育成部会と地域プロジェクト構築部会をそれぞれ統合し、下記の3分野(3部会編成)にて部会を発足させることで了承されました。
地下利用促進専門部会(仮称)
都市再構築専門部会(仮称)
地域プロジェクト構築専門部会(仮称)
また、平成10年度新部会の広報部会(仮称)について、業務運営要領(案)ならびに部会長、副部会長をはじめとする委員名簿(案)の説明があり、これに基づき部会を発足させることで了承されました。
平成11年度の研究テーマ募集については、企画ワーキンググループからの提案に基づき、環境保全、都市再構築、新産業創出に資するシステム、ならびに臨時大深度地下利用調査会の最終答申などを地下利用に係わる研究テーマ提案分野のキーワードとして加えることで承認されました。
最後に、当協会における行事等について、研究成果発表会、エンジニアリング功労者表彰、設立20周年記念事業の説明・紹介が行われ閉会となりました。
平成10年度研究企画委員会の構成は、下表のとおりです。
平成10年度 研究企画委費会名簿 (H10.6.23現在 敬称略・順不同)
|
職務
|
会社名
|
氏 名
|
所属・役職
|
|
委員長
|
清水建設㈱
|
瓜生喜久雄
|
常務取締役
|
|
委員
|
NKK
|
佐藤 透
|
エンジニアリング・技術総括部 部長
|
|
*〃
|
㈱大林組
|
友石 研二
|
土木技術本部企画部 部長
|
|
〃
|
鹿島建設㈱
|
長岡 義麿
|
土木技術本部技術部 部長
|
|
*〃
|
川崎重工集㈱
|
野原 清志
|
土木プラント部 部長
|
|
〃
|
㈱クボタ
|
佐藤 宏志
|
素形材技術部長
|
|
*〃
|
㈱熊谷組
|
森 清就
|
エンジニアリング本部
Re-エンジグループ部長
|
|
〃
|
KOMATSU
|
古川 健
|
経営企画室 技術統括部長
|
|
〃
|
新日本製鐵㈱
|
福田 弘明
|
参与開発技術部長
|
|
〃
|
住友電気工業㈱
|
畑 良輔
|
電力システム技術研究所長
|
|
〃
|
㈱ダイヤコンサルタント
|
駒野 健二
|
常務取締役 営業本部長
|
|
〃
|
東京ガス㈱
|
大津賀 久夫
|
営業総括部 供給企画グループマネージャー
|
|
〃
|
東京電力㈱
|
高辻 哲
|
建設部火力土木グループ
グループマネージャー
|
|
〃
|
日揮㈱
|
加畑 長昭
|
プロジェクトシステム本部 副本部長
|
|
〃
|
日鉱金属㈱
|
宇野 智
|
取締役資源開発部長
|
|
〃
|
㈱日立製作所
|
曽野 黎二
|
システム事業部長付 取締役事業部長
|
|
〃
|
三菱地所㈱
|
磯村 栄治
|
建築業務部 副長
|
|
〃
|
三菱工業㈱
|
高橋 清
|
汎用機事業本部 建設機械部部長
|
*印:新委員

■センター運営会議報告■
平成10年度の第1回センター運営会議が6月24日(木)に開催されました。山口専務理事の挨拶の後、新委員の紹介があり、委員長には服部正幸氏(新日本製鐵㈱ 常務取締役)が昨年度に引き続き就任されました。運営会議は、服部委員長以下37名の委員で構成されています。新委員ならびに委員構成は、右表のとおりです。
開会にあたり、委員長の挨拶の後、来賓を代表して通商産業省環境立地局産業施設課長谷重男氏より、「臨時大深度地下利用調査会の最終答申が5月27日に提出され、計画段階から大深度地下利用を考慮できる内容となっていること、また、国土庁では早期法制化の準備を進めており、次期通常国会に法案を提出予定であることから、大深度地下利用における実際の事業化に向け、当地下センターでも良い知恵を出してもらいたい」とのご挨拶をいただきました。
当日の会議は、理事会付議事項としての議題について報告・審議が行われました。議事内容は、以下のとおりです。
議題1:平成9年度卒業報告および決算報告にについて
議題2:平成10年度事業について
議題3:平成11年度テーマ募集について
議題4:平成10年度年間活動計画他について
平成9年度事業報告(案)ならびに決算報告(案)について承認された後、平成10年度事業について、日本自転車振興会補助事業の分科会テーマ4件、プロジェクト計画策定テーマ2件(内1件未定)の内容説明があり、了承されました。また、地下利用推進部会の改編(3部会編成)ならびに本年度より新規に発足する広報部会(仮称)について報告があり、了承されました。
次いで、平成11年度テーマ募集、平成10年度当センターの年間活動計画について審議がなされ、いずれも承認されました。
その他、当協会の本年度の主な行事等について説明・紹介があり閉会となりました。
平成10年度 運営会議委員名簿 (H10,6,24現在 敬称略・順不同)
|
職務
|
会社名
|
氏 名
|
所属・役職
|
|
委員長
|
新日本製鍼㈱
|
服部 正幸
|
常務取締役
|
|
委員
|
石川島播磨重工業㈱
|
中藤 信
|
専務取締役
|
|
〃
|
NKK
|
山鹿 素雄
|
特別顧問
|
|
〃
|
㈱荏原製作所
|
谷島 昶
|
特別顧問
|
|
〃
|
大阪ガス㈱
|
遠藤 彰三
|
専務取締役
|
|
〃
|
㈱大林組
|
伊丹 孝
|
常務取締役
|
|
*〃
|
鹿島建設㈱
|
高野 耕輔
|
常務取締役
|
|
*〃
|
川崎重工業㈱
|
宇野 正
|
代表取締役専務
|
|
〃
|
関西電力㈱
|
伊藤 俊一
|
常務取締役
|
|
〃
|
㈱クポタ
|
富田 勝三
|
代表取締役社長
|
|
〃
|
㈱熊谷組
|
平沢 秀男
|
取締役
|
|
*〃
|
㈱神戸製鋼所
|
山下 文男
|
取締役
|
|
〃
|
KOMATSU
|
高松 武彦
|
顧問
|
|
〃
|
清水建設㈱
|
瓜生喜久雄
|
常務取締役
|
|
〃
|
住友重機械工業㈱
|
上野山泰史
|
常務取締役
|
|
〃
|
住友電気工業㈱
|
位高 光司
|
常務取締役
|
|
〃
|
大成建設㈱
|
伊藤 善栄
|
常務取締役
|
|
〃
|
㈱竹中工務店
|
小早川洋太郎
|
取締役副社長
|
|
〃
|
中部電力㈱
|
宮口 友延
|
取締役
|
|
〃
|
千代田化工建設㈱
|
鯨井 鉀一
|
常務取締役
|
|
〃
|
電源開発㈱
|
網野 定三
|
常務取締役
|
|
〃
|
東京ガス㈱
|
山口 靖之
|
常務取締役
|
|
〃
|
東京電力㈱
|
田村 滋美
|
常務取締役
|
|
*〃
|
東洋エンジニアリング㈱
|
東條 洵
|
取締役
|
|
〃
|
戸田建設㈱
|
八木 規夫
|
取締役
|
|
〃
|
㈱新潟鐵工所
|
齋藤洋二郎
|
取締役
|
|
*〃
|
日揮㈱
|
岡田 剛
|
専務取締役
|
|
〃
|
日鉱金属㈱
|
石川 峯生
|
専務取締役
|
|
*〃
|
㈱間組
|
山口 靖紀
|
取締役
|
|
〃
|
㈱日立製作所
|
浜田 邦雄
|
取締役副社長
|
|
〃
|
㈱日立製作所
|
浜田 邦雄
|
取締役副社長
|
|
〃
|
日立造船㈱
|
谷越 敏彦
|
取締役副社長
|
|
*〃
|
富士電機㈱
|
谷 恭夫
|
取締役
|
|
〃
|
三井海上火災保険㈱
|
水谷 圭甫
|
専務取締役
|
|
〃
|
三井鉱山エンジニアリング㈱
|
佐藤 實
|
常務取締役
|
|
〃
|
三井造船㈱
|
小役丸純幸
|
取締役
|
|
〃
|
三菱地所㈱
|
田中 清治
|
技術開発室長
|
|
*〃
|
三菱重工業㈱
|
広瀬 正典
|
取締役
|
*印:新委員

■平成10年度社会開発システム策定およびプロジェクト計画策定等の調査研究スタート■
本年度の「社会開発システム策定事業(分科会)」ならびに「社会開発プロジェクト等の計画策定および推進事業(プロジェクト計画策定)」として、昨年度に引き続き下記テーマの調査研究がスタートしましたので、その概要をご紹介します。
(実施体制は、GECニュース第96号,101号に掲載)
○深部地盤直接 蓄熱システムに関する調査研究(分科会)
二酸化炭素等による地球の温暖化や冷房排熱等による都市規模のヒートアイランドこ関する問題は、深刻な問題として顕在化している。居住空間の快適性を増すために冷暖房はますます普及しているが、通常は冷暖房のために化石燃料が使用され、二酸化炭素排出の増加やヒートアイランド化の要因となっている。本調査研究では、都市部の大型ビルの下部にある軟弱地盤を対象に、垂直ボアホールを掘削して、夏に蓄熱し、冬に熱回収して熱を暖房・給湯の主熱源として用いる深部地盤直接蓄熱システムと遠隔地の利用可能エネルギーを熱輸送して総合利用を図るシステムを提案する。
昨年度は、低コスト型ボアホール建設法の開発、地中の熱流体移動予測計算法の開発、システムシミュレーションの実施、蓄熱利用システムの開発について調査研究を行った。本年度は、地下水流影響抑制手法について調査するとともに、安価な工法で埋設できる範囲の深さまでを蓄熱領域として試算し、これに熱輸送システムの検討、経済性・環境保全性の評価を加え、本提案の実現可能性についてまとめる。
(6月2日:第1回分科会開催)
|
○新燃料(超重電油)の地下貯蔵システムの可能性に関する調査研究(分科会)
電力各社では燃料の多様化に積極的に取り組んでおり、その一環として超重質油をエマルジョン化した新しい液体燃料が注目を浴びている。このような新燃料は、コストが安価なことや非危険物であることなどの特徴から電力事業での火力発電用燃料として検討対象になるなど、近年その消費量は増加傾向にある。本調査研究では この新燃料を対象として既存の地上式タンクに比較して簡易で新しい地下貯蔵システムを提案する。
昨年度は、この新しい火力燃料を対象とした地下貯蔵システムについて、新しい貯蔵機構を提案するとともに、その貯蔵システムに関する技術面、安全管理面および経済面からの成立可能性の概略検討を行った。本年度は、検討条件の設定、土木構造物の概略設計、プラントシステムの概略設計、袋体の検討、経済性の検討および安全・維持管理方法等に関する検討を行い、さらに具体的なケーススタディを実施する。
(6月24日:第1回分科会開催)
|
○廃棄物を中心とする博覧会地下空間利用に関する調査研究(プロジェクト計画策定)
2005年、愛知県瀬戸市において「新しい地球創造:自然の叡智」をテーマに国際博覧会が開催される。この博覧会は従来の一過性のイベントではない長期的地域整備の一環として位置づけられており、人間の営みと自然環境との調和を重視した環境共生型地域社会の形成を目指している。また、会場となる瀬戸市は我が国を代表する丘陵地帯としての特徴をもっており、基盤整備においては新たな空間利用の形態が求められている。本調査研究では、自然環境との両立、将来の新住市街地整備を考慮した博覧会施設のあり方を提案する。
昨年度は、地上と地下との使い分け、環境共生型の最新技術に焦点をあてた調査を幅広く行い基礎データを整理した。本年度は、博覧会ならびに将来の新住市街地にて発生する廃棄物や下水の量を予測するとともに、立地条件や現状の処理方式を考慮した上で、収集輸送手段ならびに最新の廃棄物・下水処理技術を検討し、博覧会の理念に適合した地下空間利用施設について、その可能性と実現に向けた提案をまとめる。
(6月11日:第1回委員会開催)
|

■臨時大深度地下利用調査会の最終答申まとまる■
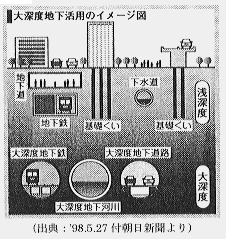
「大深度地下」の有効利用策を検討していた「臨時大深度地下利用調査会」の最終答申がまとまりましたので、概要をご紹介します。
答申では、大深度地下を「通常は利用されない地下空間」と定義し、具体的には、
①地下室の建設に支障がないよう地表から40mの深さ
②建築物の基礎杭の設置に支障がないよう支持層から10m程度の深さ
と二つの場合を想定し、「いずれか深い方から下の空間」としています。なお、こうした地下空間で公共機関が道路や鉄道、通信、ガス、上下水道などの社会資本整備を行う際、地上の土地所有権に対する補償は、井戸や温泉があったり、具体的な損失がある場合を除き、原則不要としています。
また、実際に使用する場合は、
①事業の公益性
②大深度地下を使用する必要性
③適正かつ計画的な利用に適合すること
④大深度地下での事業であること
⑤既存の建築物に悪影響を与えないこと
⑥適用事業の種類に該当すること
⑦事業者に事業遂行能力があること
などを審査し、行政庁が事業者に対し「公法上の使用権」を与えるとしています。
今後は、「大深度地下利用法案(仮称)」がまとめられ、早ければ来年の通常国会に提出される予定です。

■会員の皆様へのお知らせ■
○平成11年度研究テーマの募集について
ただいま、平成11年度の研究テーマを募集中です。詳細は、各連絡担当者へ送付してありますので、地下空間の開発・利用を促進するテーマの提案をお願いいたします。
|
募集区分:
|
①社会開発システムの策定に係わる調査研究テーマ(分科会テーマ) |
|
②社会開発プロジエクト等の計画策定・推進に係わる調査研究テーマ
(プロジェクト計画策定テーマ) |
|
応募期限:
|
平成10年8月20日(木) |
|
応募/問合先:
|
地下開発利用研究センター 技術開発第1部 山路俊文
(TEL:03‐3502-3671/FAX:03‐3502-3265) |
○平成10年度エンジニアリング功労者表彰候補の推薦について
当協会では、エンジニアリング産業の振興発展に貢献し、その功績が特に顕著であると認められる方々に対して表彰を行っております。
本年度の特別テーマは、「廃棄物の処理・資源化」です。
なお、詳細は各連絡担当者へ送付してありますので、今年度のこの賞に相応しい候補について推薦書の提出をお願いいたします。
締切り日:平成10年7月10日(金)
提出先:(財)エンジニアリング振興協会 功労者表彰事務局
問合先: 同 上 鈴木,溝口,高橋,小倉 (℡:03-8502-4441/FAX:03-3502-5500)

|