|

第117号/1999.6
■研究成果発表会'99 開催のお知らせ
■地下利用推進部会活動状況報告
■会員の皆様へのお知らせ
■新聞記事からの紹介
■研究成果発表会'99開催のお知らせ■
来る7月6日(火)~9日(金)の4日間にわたり下記のとおり「研究成果発表会 '99」を開催いたします。本成果発表会は、当協会における平成10年度の委員会、研究会等の研究成果を発表いたしますので、是非多数の方々にご参加をいただきたく、ご案内申しあげます。なお、地下開発利用研究センターのセッションは、7月9日(金)となっております。
1.会 期:7月6日(火)~7月9日(金)の4日間
2.会 場:当協会 6階CDE会議室
3.参 加 費:無 料
4.定 員:120名(定員になり次第締め切らせていただきます。)
5.申込要領:
①必ず所定の申込用紙(会員企業の各連絡担当者に別途配付済みですが、事務局にも
あります。)に取りまとめ、FAXあるいは郵送にてお申し込みください。
②申込責任者名を必ずご記入ください。
③参加予定のセッション欄を○で囲んでください。
④申込者が定員を越える場合は締め切りますが、参加登録できなかった場合に限り
ご連絡いたします。連絡のない場合は参加登録できたものとお考えください。
⑤申込締め切り日は、6月25日(金)です。
6.問合せ先:GEC 近藤/中村 TEL:03-3502-3671/FAX:03-3502-3265
|
7月9日(金):地下開発利用研究センター/石油開発環境安全センターのプログラム |
|
9:30 |
開場(受付開始) |
|
10:00 |
開会の挨拶(山口専務理事) |
|
10:10~11:05 |
D-1 海洋石油開発危機管理 - 定量的リスク評価
平成10年度分科会委員 坂本 隆(新日本製鐵㈱) |
|
11:05~12:00 |
D-2 海底仕上げ坑井保安技術調査
平成10年度分科会委員 岡田 陽(日本オイルエンジニアリング㈱) |
|
12:00~13:00 |
昼休み |
|
13:05~13:50 |
D-3 新燃料(超重質油)の地下貯蔵システムの可能性に関する調査研究
平成10年度分科会作業部会部会長 傅田 篤(清水建設㈱) |
|
13:50~14:35 |
D-4 廃棄物を中心とする博覧会地下空間利用に関する調査研究
平成10年度分科会作業部会リーダ 山本 光起(㈱竹中工務店) |
|
14:35~14:45 |
10分休憩 |
|
14:45~15:30 |
D-5 微振動対策を必要とする施設の地下空間利用に関する調査研究
平成10年度分科会事務局 山崎 武久(㈱竹中工務店) |
|
15:30~16:15 |
D-6 下水処理場等から発生する未利用ガスを利用するガスタービン用
低NOx燃焼機器の開発
平成10年度研究連携機関代表 小林 英夫(石川島播磨重工業㈱) |
|
16:15~17:00 |
D-7 深部地盤直接蓄熱システムに関する調査研究
平成10年度分科会委員 酒井 寛二(㈱大林組) |
|

■地下利用推進部会活動状況報告■
○地下利用に関する講演会開催報告
地下利用推進部会では、平成11年度活動の一環として、5月13日(木)に、第2部会(都市構築専門部会)主催で、第1と第3部会の参加希望者も含めて、講演会を開催しました。当日は、名古屋大学工学研究科の西淳二教授・博士をお迎えし、「地下空間の快適性に関する地下施設の評価」と題して、地下空間の快適性評価やデザインについて、それらの問題点も含めて、ご講演いただきました。以下に、その概要を紹介します。
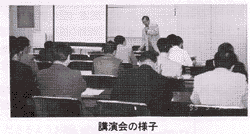 1.地下空間の快適性や地下施設の評価は、簡単には答が得られない。評価対象、評価項目、評価者(事業者orユーザ)により異なり、法規制やコスト等の制約があるため、バランスのよい評価指標を決めて、総合評価を行う必要がある。地下空間評価の課題としては、総合評価の方法を考え、将来の地下施設へ反映していくことである。特定の専門分野で終わらないで、エンジニアリング振興協会のように、色々な人が集まる所で、検討していくのに適している分野である。安全や安心も含めて、どのような空間設計ができるかが大事である。 1.地下空間の快適性や地下施設の評価は、簡単には答が得られない。評価対象、評価項目、評価者(事業者orユーザ)により異なり、法規制やコスト等の制約があるため、バランスのよい評価指標を決めて、総合評価を行う必要がある。地下空間評価の課題としては、総合評価の方法を考え、将来の地下施設へ反映していくことである。特定の専門分野で終わらないで、エンジニアリング振興協会のように、色々な人が集まる所で、検討していくのに適している分野である。安全や安心も含めて、どのような空間設計ができるかが大事である。
2.将来の地下空間を計画する場合は、「地上に近い空間」、「地上に似せた疑似空間」、「地下らしい地下」の3つを考慮するとよい。地下の出入り口も、重要な要素である。地下では、時間の経過がわからなくなり、動きもなくなるため、植物、水、動物等を用いて変化を与えたり、開放的にして地下に対する抵抗感を無くすようにする等が大事である。入り口を大きな広場にしたり、照明を時間とともに変化させたり、地上や地下の様子が一目でわかるようにする等の方法がある。
3.地下空間のデザインプロセスとしては、計画~設計~管理・運営となるが、計画のステップで特に改善の余地がある。個人の能力に対してでなく、都市全体計画等の大きなところとつながってくる問題である。インフラ整備のやり方としては、機能だけを考えるといいものはできない。また、地下の柱は邪魔であるがはずせないため邪魔でないようにするなど、地下の持つ欠点を踏まえた設計も必要である。

■会員の皆様へのお知らせ■
○第214回サロン・ド・エナ開催のご案内
日 時:平成11年6月16日(水)17:30~19:00(講演会) 19:00~20:00(懇親会)
場 所:当協会6階CDE会議室
講 師:杉田 定大 氏(通産省 産業政策局 新規産業課 課長)
テーマ:「日本版PFI事業の推進-PFI推進法案の理念と運用等について-」
申込要領:FAXで事務局へお申し込み下さい。申込多数の場合は先着順で締め切らせていただきます。
《講演要旨》
民間事業者主導による社会資本の整備等(いわゆる「日本版PFI」)を推進することは、財政負担の軽減を通じ財政構造改革に資するとともに、民間事業者が起業家精神を持って新規産業の創出を図るとの点で、極めて重要です。
このPFI事業の推進にあたり、その理念と運用等について詳しくお話をしていただきます。
○「地方の活性化をめざした地下空間利用研究会」講演会のご紹介
地方の活性化をめざした地下空間利用研究会(会長 稲田 義紀 愛媛大学教授)では、平成11年度総会に引き続き、下記の講演会が開催されます。
日 時:平成11年6月4日(金) 13:20~16:55
場 所:愛媛県県民文化会館 真珠の間A
松山市道後町2丁目5-1 TEL:089-923-5111
内 容:①エネルギーの地下備蓄および供給システムについて
勝山 邦久 氏(通産省 工業技術院 資源環境技術総合研究所 地殻工学部 部長)
②地下空間の拡幅技術の事例と提案
粕谷 太郎 氏(鉄建建設(株)エンジニアリング本部技術企画部 部長)
③岩盤地下水取水システム
百田 博宣 氏(清水建設(株)技術研究所 主席研究員)
問合先:愛媛大学工学部 環境建設工学科 岩盤工学研究室内「地下利用研究会」事務局
TEL:089-927-9823・9842 / FAX:089-927-9842

■新聞記事からの紹介■
○地下ヒートシンクによる地域冷暖房で真夏の平均気温を3℃押し下げ
('99/5/12日付 日本工業新聞より)
東京大学工学部の小宮山宏教授らの研究グループは、ヒートアイランド現象を抑制する有効な対策として、土中にU字菅等を熱交換器として埋設し、深度200m程度の土壌を温冷熱源として利用できることを、コンピュータシュミレーションで明らかにした。とくにエネルギー消費の大きい地域で夏季ヒートアイランド現象の抑制対策として期待されている。
シュミレーションの対象エリアとしては西新宿地区1km四方を設定した。資源環境研究所が開発した街区気象モデルを利用してシミュレーションすると、個別に冷暖房設備を設けてビル屋上から排熱する場合に比べ、地下ヒートシンクシステムによる地域冷暖房システムを採用すると、西新宿地区の8月の平均気温を3℃押し下げられる効果があると推定された。

編集後記第117号より、深江主任研究員に代わり、本紙の編集を担当させていただきます。生まれは福井県の山の中、東京での暮らしは初めてという単身赴任中の田舎者です。カルチャーショックにかからないよう、マイペースで行こうと思います。なお、会員皆様の声を取り入れた編集を心がけたく、GECニュースに関するご意見、ご要望など、お気づきの点がございましたら、事務局までFAXにてご連絡くださるようお願い申しあげます。
「GECニュース係り」(技術開発第一部;輪違) |

|