|

第120号/1999.9
■設立10周年を迎えて
■地下開発利用研究センターの10周年に寄せて
○GECニューストピックス抜粋
○事業活動を振り返って
■地下センター10年のあゆみ
■文明の源流-古代からの地下と地上の使い分け-
■会員の皆様へのお知らせ
■設立10周年を迎えて■
エンジニアリング振興協会 理事長 園田 保男
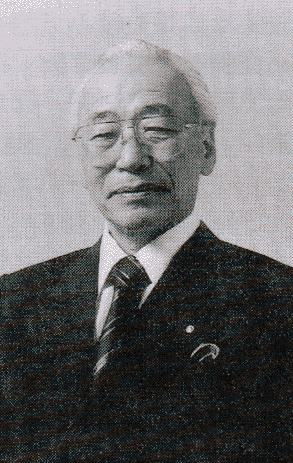 1989年9月に地下開発利用研究センターが発足して以来、皆様から暖かいご支援を頂戴し、ここに10周年を無事迎えることができました。 1989年9月に地下開発利用研究センターが発足して以来、皆様から暖かいご支援を頂戴し、ここに10周年を無事迎えることができました。
この間当センターは、地下空間開発利用技術に関するマスタープランの策定や下間利用ガイドブックの編纂、大深度地下空間開発技術の研究開発をはじめとする地下空間の開発利用に関する調査研究、社会開発システムの研究開発、社会開発プロジェクトの計画策定とその推進、数多くの受託事業、広報活動等様々な活動を積極的に展開してまいりました。
また、設立10周年を機に、これまでの研究開発等の成果を広く普及するべく、当センターのホームページを先般開設したところであります。
このように幅広く事業を進めることができましたのも、偏に関係官庁、関係諸機関および学界の皆様のご指導とご支援、産業界の皆様のご協力の賜であり、厚くお礼申し上げます。
振り返ってみますと、当センターが設立された10年前には、ジオフロントとして地下空間が脚光を浴びていましたものの、1991年に頂点に達していたわが国都市圏の地価が急激に下落した所謂「バブルの崩壊」により、地下空間利用に対する社会情勢も大きく変化致しました。
この結果、地下空間利用の過熱ムードは沈静化したものの、技術の進歩と相俟って、大都市の過密を改善することを目指した地下空間利用や、石油・液化石油ガスの備蓄といったエネルギー分野の地下利用が着々と進展していることは皆様ご承知の通りであります。
また、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災では、過密都市において、市民を守る空間が地上だけでは既に不足していることが、不幸にも現実の形で突きつけられ、地下空間には安全性・信頼性の高い社会資本が作り易いことも再認識されるに至りました。
21世紀を目前にし、「高度情報化」に加え「高齢化・少子化」といった社会構造の基盤が大きく変化する中にあって、経済成長の確保、エネルギーの安定供給、環境課題への対策というトリレンマの解決をめざして、次世代に引き継ぐ都市と、産業の新たな発展の基盤づくりが強く求められています。
このような新しい社会の要請を受け、昨年5月に「大都市地域では、通常利用されない大深度地下を社会資本整備に使うことが必要である。」とする臨時大深度地下利用調査会による答申が出され、これに基づき大深度地下の使用権を法制化するための検討が現在行われており、地下空間利用に係る周辺整備が着々と進んでいます。
関係各位の地下空間利用に対するご理解とご協力に改めてお礼申し上げますとともに、今後とも当センターに一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

■地下開発利用研究センターの10周年に寄せて■
通商産業省環境立地局 産業施設課長 平野 正樹 氏
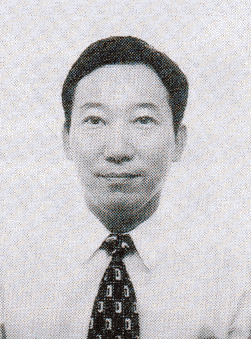 平成元年に地下開発利用研究センターが、財団法人エンジニアリング振興協会の付置機関として発足して以来、順調な発展を遂げられ、このたび10周年を迎えられましたことに対し、心からお慶び申し上げます。 平成元年に地下開発利用研究センターが、財団法人エンジニアリング振興協会の付置機関として発足して以来、順調な発展を遂げられ、このたび10周年を迎えられましたことに対し、心からお慶び申し上げます。
皆様御高承のとおり、昭和60年代前半から、社会活動や経済活動の新たなフロンティアとして地下空間が注目を集め、昭和63年6月には地下空間利用技術の開発促進を含めた総合土地対策要綱が閣議決定されるなど、地下空間に関する様々な議論が行われました。その過程において、より安全で経済的な地下空間利用の技術開発などを行うことを目的として、地下開発利用研究センターが発足したと承っております。
地下開発利用研究センターは、発足以来、①地下空間開発利用に関するマスタープラン・ガイドブックの策定 ②大深度地下空間開発技術の研究開発の着実な成果の積み上げ ③地下空間利用システムの研究開発と実証実験 ④地下空間の開発利用に関する課題の調査研究 ⑤地下空間プロジェクトの計画策定 などを推進し、我が国経済・社会の新たな発展のために活動してこられました。更にこれらの成果は、国、地方公共団体などからの種々の受託事業に活用されているとともに、地下空間に関する多岐にわたる情報の発信を行うことを通じて、社会ニーズの実現に広く役立てられており、その御尽力に改めて心から敬意を表するものであります。
本来、地下空間は、騒音、振動などの遮蔽性、恒温性、耐震性などに優れ、無限の可能性を有する身近なフロンティアであり、国民生活と経済の課題解決のために大きな可能性を与えるものであります。
私は、最近、3年間の英国勤務を終えて帰国したところですが、ロンドンでは明治維新前の1863年1月10日に既に世界最初の地下鉄が開業する等、古くから将来を見据え、地下空間の利用が積極的に図られてきており、彼らの先見性に驚かされていたところです。
最近、平成10年5月の「臨時大深度利用調査会」答申を踏まえ、大深度地下の適正かつ計画的利用の確保と公共的利用の円滑化を図る観点から、技術・安全・環境面の課題を含め現在法制化の整備を政府部内で検討しているところでありますが、地下空間の利用促進は、特に、空間スペースが限られた我が国において新たな経済、社会活動の場を拡げる上で、また、豊かさとゆとりの実現、活力ある経済社会の構築のため大変有望な分野であり、21世紀に向けてのフロンティアと位置付けられます。今後、地下開発利用研究センターの果たすべき役割は益々重要であると確信するとともに、一層の御活躍を期待するものであります。
最後になりましたが、新分野の開拓に御尽力いただいた学識経験者の方々や関係業界の皆様に深く敬意を表しますとともに、地下開発利用研究センターの一層の御発展を祈念いたしましてお祝いの言葉に代えさせていただきます。

■地下センター10年のあゆみ■
○GECニューストピックス抜粋
創刊号/1989.9 センター設立披露、第1回センター運営会議開催
第3号/1989.11 第1回マスタープラン専門委員会開催
第6・7合併号/1990.2・3 大深度地下空間開発技術受託(NEDO)、大深度地下空間開発委員会発足
第54号/1994.2 地下利用推進部会発足
第60号/1994.8 石油ガス国家備蓄基地予備調査受託(石油公団)、備蓄プロジェクト室設置
第61号/1994.9 「地下空間」利用ガイドブック完成
第82号/1996.7 大深度地下空間開発技術「ミニドーム」完成披露
第95号/1997.8 大深度地下空間開発技術成果発表会
第98号/1997.11 エネルギー使用合理化鉱山システム等開発システム受託(金属鉱業事業団)
エンジニアリング功労者(特別テーマ「地下空間の利用推進」)表彰
第106号/1998.7 臨時大深度地下利用調査会の最終答申
第108号/1998.9 地下情報化推進部会発足
第116号/1999.5 地下センターホームページ開設
○事業活動を振り返って
「地下センターとの10年のおつきあい」
東京大学名誉教授 地圏空間研究所 代表 小島圭二 氏
私と地下センターとのおつきあいの遠因は、1970年代のオイルショックがきっかけの、石油の国家備蓄プロジェクト、まだ地下センターのないエン振協の時代にさかのぼる。私の「新しい地下利用」へのかかわりの起点であり、エン振協とのつきあいの最初であった。
この頃、大都会でも、地下の高騰が続き、都市の機能と環境の整備が思うにまかせず、このネックの解消に、地下の利用が期待された。地下の所有権を制限する法整備の機運が高まったことも加えて、ここにも「新しい地下利用」の提案が一気に開花する動機があった。いわゆる「地下利用フィーバー」である。通商産業省の「大深度地下利用懇談会」(1988)も、これに火をつけた一つである。この頃既に、エン振協では、地下利用関連の委員会が活発で、この懇談会にも重要な資料を提供した。上記の懇談会や委員会のいくつかのまとめ役として我田に引水すれば、これらの実績が、1989年の「地下センター」の設立に結びついた一因と思われる。
そして設立後の地下利用マスタープラン、ガイドブックの作成、この辺からが、地下センターとのつきあいのはじまりである。
通商産業省工業技術院の大型プロジェクト「大深度地下開発技術」いわゆるジオドームプロジェクトは、地下センターの最初の大仕事であり、この立ち上げにかかわったことから、私のおつきあいがまた増えた。地下センターの研究・開発のエネルギー源は、各種異業種が集まった「るつぼ」にあると言えよう。
設立の当初、地下権の法整備とジオドーム構想を世界に紹介し、また異業種間で、世界の地下空間利用の知見を共有する目的で、多くの海外調査が実施された。これらの海外調査に参加する機会を得たことが、地下センターとのつきあいをさらに深める一因となった。異業種間を結びつけるつきあい"宴振協"の重要さを改めて痛感した一駒でもあった。ミネソタ会、ストックホルム会は、今なお続く情報交換の場である。
世界の大問題、人口の急増/都市集中、エネルギー、食糧と環境、「地下利用フィーバー」以来叫ばれている地下利用の動機は変わっていない。ただ世の中のパラダイムが急激に変わりつつある。「地域社会の合意」、「地域社会からの提案」がより重要視される世の中に変わりつつある。そして「地下利用フィーバー」の頃の機能中心から、環境・防災へのシフトも見られる。地下センターの役割も変化しつつある。従来の技術の専門家の思い込みを脱して、地域社会が、地下に安心して入ってこられる環境の創出、関連技術としての「地下環境変化の予測」、「地下の可視化とモニタリング」そして「修理と改造の技術」、これらのシステムを組み込んだ地下利用の実現へ向けた数ある地下利用のRethinking。第二の「地下利用フィーバー」へ向けて、地下センターとのつきあいは、まだまだ続きそうである。
地下センター10周年を心からお祝い申し上げるとともに、今後のますますの進展を期待する次第である。
「LPガス国家備蓄の推進」
石油公団 備蓄計画部長 織山 純 氏
地下センターの設立10周年、おめでとうございます。この10年間におきます同センターの御努力に対し敬意を表しますと共に、石油公団への御協力に対しこの場をかりて御礼申し上げます。御承知の様に、石油公団の備蓄における地下空間の開発利用に関しましては、既に原油の地下岩盤貯蔵がありますが、現在、LPガスの地下岩盤貯蔵方式によります国家備蓄も検討されています。そこで、良い機会ですので、この場をお借りしてLPガスの国家備蓄計画につき最近の動きを御紹介したいと思います。
熱量等において優れ環境負荷も比較的低いエネルギーであるLPガスは、その利点から今後も着実な需要が見込まれています。一方、供給につきましては、輸入依存度が約8割に達しており、更にそのうちの約8割は中東地域から輸入されています。先の湾岸戦争の経験からも、供給の安定性がより一層確保されることが期待されています。
このような状況下において、石油公団では、1992年の石油審議会石油部会液化石油ガス分科会報告(LPガス安定供給基盤供給のあり方)を受けて、2010年度に150万トンのLPガス国家備蓄を達成するべく準備を進めています。これまでに立地可能性調査を終了した4候補地点(石川県七尾市、長崎県福島町、愛媛県波方町、岡山県倉敷市)のうち七尾地点、福島地点につきましては、地元調整等社会的条件が整ったことから1998年に立地決定を行い同年、基地の建設・操業の主体となる「日本液化石油ガス備蓄株式会社」が設立されました。
さて、LPガスの貯蔵方式としては、地上低温タンク方式と地下岩盤タンク方式を採用することとしていますが、波方計画地点と倉敷計画地点の2ヶ所においては地下岩盤タンク方式を計画しています。この貯蔵方式は、海外では既に多くの実績がありますが、LPガスの地下岩盤タンク方式につきましては、日本国内での建設実績がないため、石油公団では1986年度から1993年度にかけ倉敷市に地下備蓄実証プラントを建設して各種実験・検討を行い、安全性、操業上の実用性等について確認しました。
現在、残る候補地点の立地決定を目指し、地方自治体を通じて地元調整が着実に進められているところです。目標の150万トンの国家備蓄が達成されますと、輸入量の50日分の民間法定備蓄と併せて約80日分のLPガス備蓄体制が整うことになりますが、石油公団ではこの目標の達成へ向け、鋭意努力を続けてまいります。本事業は国家プロジェクトであり、今後とも本事業について変わらぬ御指導、御支援をお願い申し上げます。
最後に、地下センターの今後の更なる御発展を祈念いたします。
「大深度地下空間開発技術」-ジオドームの研究開発を振り返って-
コマツ 技術顧問 高松 武彦 氏
ご多分に漏れず暇を得て絵筆を持ち始めた。絵画教室に通い始めた頃は与えられたモチーフをひたすら描いて技法の習得に終始していたが、自由に自分で描きだしてからは、何を描こうかと悩みだした。静物か風景か、浅間へでも出掛けようか、千曲川を見に行こうか。それとも近くで横浜の街かと。これが決まると次は構図でまた迷うがその範囲はかなり狭められてくる。ここまで来れば、もう後は半分力仕事に入る。
下手ながら自分なりの絵を描こうとすると、何に感動しどう表現したいか、何を訴えるのか企画段階がやはり一番迷うところだ。でないと何処かで見た<絵はがき>にしかならない。不思議なことに暇つぶしで始めた趣味の筈がそのうち他人に見てもらいお世辞の一つも欲しくなるものだ。閉鎖的な自己満足だけでは長続きしない。かくしてクラブ展、同好展がおおはやりなわけだ。
さて10年を振り返り、平成元年に大深度地下空間開発技術の開発委員長に任命されたときはプロジェクトの骨子になる構想はすでにできていた。長年商品開発に携わってきた者として、新技術を備えていない物真似的商品には何の魅力も感じないばかりか軽蔑さえする。それ故にこのプロジェクトの斬新さに驚き惹きつけられた。
密集狭隘な都市で未開拓の「地下」に巨大空間を構築
し利用しようという、大胆な発想は過去の引きずられた連続的思考からは生まれない非凡なものであった。それだけに否定的な意見も多かったと思う。印象派絵画に慣れた時代にピカソに驚くと言えば言い過ぎだろうか。
高精度地下構造評価技術、大深度地下空間構築技術、大深度地下環境制御・防災技術の開発、そしてそれぞれの実証テストによる確認とが技術専門委員会ならびに開発委員会にて審議・推進を経ながら進められた。
幅広い先端技術分野を結集したこのプロジェクトは私にとって未知の技術分野も多く、自身の無知さを知らされるとともに、持ち前の好奇心を刺激するに余りあるものがあった。厚顔ながら皆様の応援でついつい最後まで引き込まれ、開発委員長をやらせていただいた。
首都圏の分散は百年の計にしても、すでに対処すべきことは山積みしている。開発した技術を使い隘路を具体的に解消してゆくことを強く望みたい。
バイオと情報が低迷している日本経済再浮上技術と云われるが、エンジニアリングは生活基盤を支える必須には変わりはない。世界に認められる革新技術の発想・企画と開発に、これからも日本の先導役としてのエンジニアリング振興協会による指針づけを期待する。
「地下利用の理念と選択に想う」-マスタープランの研究を振り返って-
清水建設㈱ 技術研究所 特別プロジェクト部 主席研究員 石崎 秀武 氏
地下開発利用研究センターが発足して最初の全会員企業が参加しての調査研究がマスタープランの策定でした。このマスタープランは地下センターが今後取り組むべきテーマ、その優先順位などを定めた、いわゆる地下センターの事業のマスタープランです。マスタープラン専門委員会(委員長:伊藤慶大教授)が設けられ、この委員会のもとにほとんど全ての会員企業から170名以上の参加者を得て部会を組織し、調査研究が進められました。この部会活動の流れは現在の地下利用促進部会までセンターの大きな事業の一つとなって繋がっています。さて、マスタープランの策定では地下利用の現状、将来予測、あるべき姿の検討などから調査研究テーマの洗い出し、優先順位の策定など2年半にわたり行われました。マスタープランの策定で特に印象に残っているのは基本問題部会で検討した「地下利用の基本理念」です。当時は現在と異なり、大深度地下利用が華々しく打ち出されたバブルの最盛期であり、ある意味では何でもかんでも地下に入れる風潮もあり、地下利用の理念も混沌としていた時代でした。このような時にこの問題に真正面に取り組んだことは特筆に値すると言えます。 マスタープランの地下利用の理念には「地下利用は社会資本の整備・充実を促進し、地上の再開発・環境改善等を進めること」を明記しており、バブル時の風潮に流されることなく現在にも通じるものとなっています。
その後、この理念は平成5年の「地下利用懇談会(座長:伊藤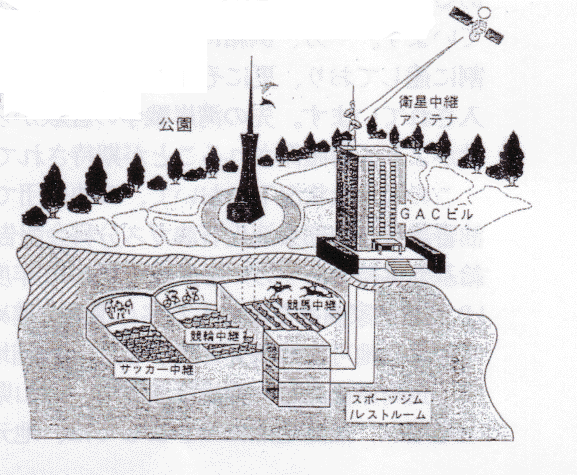 慶大教授)」において「地下空間は地上空間をより快適にするために利用するもので、地上の補完的な位置付けを持ち、社会資本整備を進めるための有効な選択肢の一つである」と言う明確な理念の先鞭をなすものでした。現在の地下利用はこの理念の前段にそった施設が着実に進んでいると思います。しかし、後段の地下が有効な選択肢になっているか、この点に関しては末だしの感があります。 慶大教授)」において「地下空間は地上空間をより快適にするために利用するもので、地上の補完的な位置付けを持ち、社会資本整備を進めるための有効な選択肢の一つである」と言う明確な理念の先鞭をなすものでした。現在の地下利用はこの理念の前段にそった施設が着実に進んでいると思います。しかし、後段の地下が有効な選択肢になっているか、この点に関しては末だしの感があります。
地下利用は地質、建築・土木、電気・機械など多くの技術あるいは業種の複合物です。これら多くの業種、技術が有機的に結合し、現在の地上立地のシステムと同様の地下立地を前提とした地下利用システムが出来ればその時が地下利用が名実共に有効な選択肢となる時だと思います。
地下センターの今後の事業活動に期待するところ大です。

■文明の源流ー古代からの地下と地上の使い分けー■
(見学報告)
人類は、代々受け継がれてきた生活の中でさまざまの文化をつくってきた。同じものに対する価値観も多様化している。こうしたことは民族の独自性(アイデンティティ)の基盤となっている。
その源流として欧州の古代人たちが地下の洞窟をどのように使っていたか、見学する機会に恵まれた。
スペインのアルタミラ洞窟はフランスのラスコー洞窟とあわせて良く知られているが、もっと古い洞窟とその壁画が発見されており、調査が続けられている。特に、名プレーヤー、バレステロスを生み出した王立ゴルフ場で名高いサンタンデールから南西35km奥に分け入ったところに、プエンテ・ビエスゴがある。ここに「プエンテ・ビエスゴの洞窟」と呼ばれ、原始芸術が見られ4つの洞窟が集まっている。
この一帯は石灰質泥岩から出来た山々が連なり、外から隔離された安全な空洞が多い。かつてイスラムの騎馬軍団が800年間にわたるイベリア半島支配から撤退する糸口となったのも、カンタブリア山脈の中のコバドンガの戦いであった。キリスト教徒の作戦基地となったのはラ・サンタ・クエバ(聖なる洞窟)であった。勝利を収めた側はやがてカスティーリャ・イ・レオン王国となり、スペイン王国に繋がる。
古代人たちに安全な暮らしを提供し、また後世でキリスト教徒を守ったのは、カンタブリアの地下空洞であったとも言えよう。説明してくれたのはムセオ・デ・プレヒストリア(先史博物館)の管理事務所、ホセさんである。調査は25の地層に分けて作業が進められ、15万年前まで溯ろうとしていると言う。これはクロマニヨン人より古く、10万年前以前のネアンデルタール人まで溯ることになる。地層の時代の差で、古代の道具の発達がみられるという。洞窟に入ると、蒸し暑い33℃の外気と違って涼しく、20℃以下である。洞窟の中の温度は変わらないので、冬は外の厳しい寒さに対して非常に暖かいそうである。入ったところは床が平坦で天井が非常に高く、ゴシックの教会のホールが続いている感じを受ける。古代人たちは地上の生活を洞窟入口の傍で営み、地上と安全な洞窟とを使い分けていたという。
洞窟内の坂道を右へ下りて行くと、まず突き当たりの壁に肩の盛り上がった野牛が描かれている。岩の割れ目に沿って全身の輪郭があり、岩の膨らんでいるところは腹部である。その上や左にも他の野牛、山羊の輪郭が描かれている。さらに奥の2番目、3番目のサラ(ホール)へ進むと、窪みの壁から低い天井部に無数の人の手、動物の頭や背などが描かれている。手を壁に当てて上から顔料を吹付けた手形は、野牛の画の中央にあるのが目立っている。これはおそらく野牛を手に入れる意味ではなかったかと言う。
4万年前から1万5千年前くらいまで、画が増やされてきているそうである。洞窟の外には食物と水があって、洞窟の中は安全で暑さも寒さも暴風雨も凌ぐことができ、記録を残すこともできた。こうして南欧の古代人たちは洞窟と水を大切にし、豊かな生活をおくっていたと言う。
但し、聴き取りの不正確なところもあろう。
いま、欧米の人達の住居を我々のものと比べると、多くは壁が厚くどっしりしていることが必要とされる傾向にある。しかし窓は小さくても良い。床の高さは地面とおなじで構わない。土足で入って当たり前である。薄暗い部屋で安らぎを感じる。こうした生活は見方を変えると、洞窟のくらしから発達したなごりとみることも出来るかも知れない。自宅の地下のホビールームや工作室などに安らぎを感じる人々も欧米には多いようである。
これに対して、日本人の我々は住居でやすらぐとき、薄い壁や軽い間仕切りでも平気である。外との接触を大切にし、窓が南に大きく開いて風通しの良い家を好む。虫の音や風のささやきに季節を感じる。床は地面よりも高くして、「草」を編んだ畳を清潔に保つ。これらは、アジア人の多くの先祖がかつて森林で暮らし、草原に降りて農耕を始めた以来のなごりではないかという意見もあるようである。もちろん、欧米の感性と我々の感覚と、どちらが良いというものではない。
我々の国は地下街や地下鉄、共同溝などが発達してきたが、地下のデザインはいま一歩と言われている。
我々に地下と地上とを使い分ける古代からの智恵がプリントされていないとしたら、今後の社会システムに
おける課題は大きいものがあろう。
(地下開発利用研究センター 研究理事 宮川 記)

■会員の皆様へのお知らせ■
○第216回サロン・ド・エナ 開催のご案内
*日 時 ;平成11年 9月16日(木)17:30~20:00 *場 所 ;当協会6階CDE会議室
*テーマ ;「荒川の水で芝川・綾瀬川がよみがえる」
-地下鉄との共同事業による芝川・綾瀬川等浄化導水事業-
*講 師 ;佐藤 郁太郎 氏 (建設省 関東地方建設局 河川部河川調整課建設専門官)
*講演要旨; 建設省の河川環境管理に対する理念、河川環境整備への取り組みの内容、具体的な河川環境整備事業のメニューについて紹介するとともに、地下鉄との共同事業とすることにより事業効果の早期発現、コスト縮減を図った地下利用の先進的な事例として、「芝川・綾瀬川等浄化導水事業」の計画概要及び施行状況について紹介する。この事業は、水質汚濁が著しい綾瀬川、芝川等の河川について、今後下水道整備等により予測される水量の低減分を荒川より補給し流況の安定を図るとともに、きれいな水を注水することで魚が生息できる水質を実現するなど河川環境の改善を目的とするもので、導水管を地下鉄トンネル内に入れ た日本で初めての事業となる。
○エンジニアリングシンポジウム'99 開催のご案内
*日 時 ;平成11年 10月20日(水)10:00~19:00 、21日(木)9:30~17:30
*場 所 ;東京国際フォーラム Bブロック7階ホールB
*テーマ ;
20日 10:00~12:00 「グローバリゼーションと情報革命-日本企業再生への戦略-」
中谷 巌 ソニー㈱ 社外取締役
13:00~14:40 「21世紀に向けての経営環境の変化と企業の経営戦略」
西室 泰三 ㈱東芝 社長
15:20~17:00 「今後のNTTグループの事業展開について」
宮津 純一郎 日本電信電話㈱ 社長
17:00~17:30 エンジニアリング功労者表彰式
17:30~19:00 親睦パーティー
21日 Ⅰ会場
「21世紀を目指すプロセス産業/エンジニアリング業のコラボレーション戦略」
9:30~10:20 「世界の動向と日本の対応(概況)」
好永 俊昭 ㈱日立製作所 原子力プラント事業部副技師長
10:20~12:00 「最新ユーザ動向の紹介」
ケン・アダムソン AEA
Technology Vice President of Product Management
13:00~14:30 「プラントサイクルに係わる情報モデルの最新動向」
ハンス・タイヘラー Fluor
Danel B.V.
15:00~16:00 「PDM実装の先例に学ぶ情報モデルの実装」
マーク・ホーン Quillion
Systems Limited CEO
16:00~17:30 「事例紹介(S社 SW PJ)」
マーク・ホーン Quilion
Systems Limited CEO
21日 Ⅱ会場
10:00~12:00 「変わりつつある環境と期待されるエンジニアリング業界」
徳久 芳郎 産業評論家
13:00~14:30 「中東、アフリカ、中央アジアの経済状況」
佐々木 良昭 拓殖大学 海外事情研究所 教授
15:00~17:30 「プロジェクトマネージャー経験者によるパネルディスカッション」
駒橋 徐 日刊工業新聞社編集委員
山田 豊 東洋エンジニアリング㈱
秋山 敬二 日揮㈱
渡辺 好之 千代田化工建設㈱
*申込方法;「参加申込み葉書」に必要事項をご記入の上、郵送あるいはFAXにてお早めにお申し込み下さい。
*申込期限;平成11年 10月 8日(金)
*参加費 ;シンポジウム:21,000円、親睦パーティー:10,500円 (消費税込み)
*申込・問合先;(財)エンジニアリング振興協会 シンポジウム事務局 上原/伊藤/志村
(TEL:03-3502-4441、FAX:03-3502-5500)
○平成11年度国内見学会のご案内
当センターでは、事業の一環として地下利用施設の見学会を毎年度実施しております。今年度は、中部地方の各地下利用施設について、関係各所のご理解、ご協力を得て見学させていただくことになりました。詳細は別途、各連絡担当者宛にお送りしますので会員各位は、この機会に是非ご参加くださるようご案内申し上げます。
*月 日; 平成11年11月10日(水)~12日(金) (2泊3日)
*見学先;福井県大野郡:中竜鉱山跡(鉛・亜鉛の鉱山の地底探検)→
岐阜県高山市:高山祭りミュージアム(地中大空間)→
岐阜県益田郡:中部電力馬瀬川水力発電所(揚水式地下発電所)→
岐阜県土岐市:
東濃鉱山 (地層科学研究)→
岐阜県本巣郡:根尾谷断層(国の特別天然記念物)→
愛知県名古屋市:松ヶ枝変電所(大規模地下変電所)
*定 員 ; 40名(先着順/申込期限:平成11年10月1日(金))
*申込・問合先; 地下開発利用研究センター事務局 安宅/中村
(TEL:03-3502-3671、FAX:03-3502-3265)

|

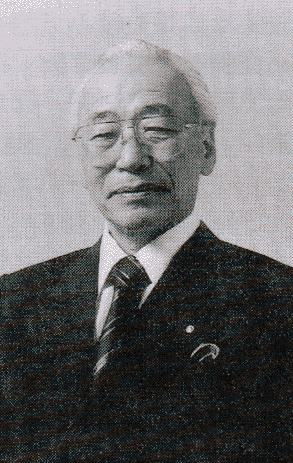 1989年9月に地下開発利用研究センターが発足して以来、皆様から暖かいご支援を頂戴し、ここに10周年を無事迎えることができました。
1989年9月に地下開発利用研究センターが発足して以来、皆様から暖かいご支援を頂戴し、ここに10周年を無事迎えることができました。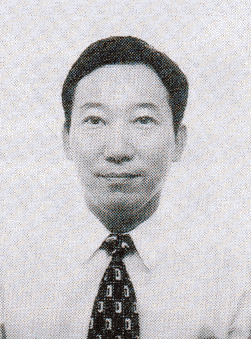 平成元年に地下開発利用研究センターが、財団法人エンジニアリング振興協会の付置機関として発足して以来、順調な発展を遂げられ、このたび10周年を迎えられましたことに対し、心からお慶び申し上げます。
平成元年に地下開発利用研究センターが、財団法人エンジニアリング振興協会の付置機関として発足して以来、順調な発展を遂げられ、このたび10周年を迎えられましたことに対し、心からお慶び申し上げます。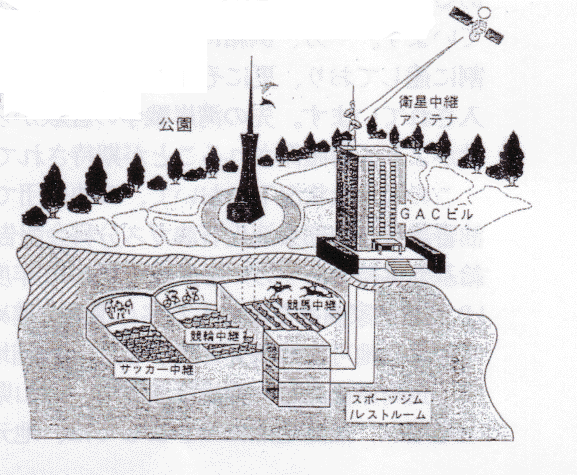 慶大教授)」において「地下空間は地上空間をより快適にするために利用するもので、地上の補完的な位置付けを持ち、社会資本整備を進めるための有効な選択肢の一つである」と言う明確な理念の先鞭をなすものでした。現在の地下利用はこの理念の前段にそった施設が着実に進んでいると思います。しかし、後段の地下が有効な選択肢になっているか、この点に関しては末だしの感があります。
慶大教授)」において「地下空間は地上空間をより快適にするために利用するもので、地上の補完的な位置付けを持ち、社会資本整備を進めるための有効な選択肢の一つである」と言う明確な理念の先鞭をなすものでした。現在の地下利用はこの理念の前段にそった施設が着実に進んでいると思います。しかし、後段の地下が有効な選択肢になっているか、この点に関しては末だしの感があります。