|

第123号/1999.12
■「地中地盤蓄熱システム技術先導研究開発」の活動状況報告
■平成11年度国内見学会報告
■会員の皆様へのお知らせ
■「雪冷蓄熱システムの多目的利用に関する調査研究」の委員会活動状況報告
■新聞記事からの紹介
■「地中地盤蓄熱システム技術先導研究開発」の活動状況報告■
当センターでは新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)殿より標記の先導研究開発を受託決定し、研究を開始しましたので以下に概要を報告します。
1. 先導研究の概要
(1) 先導研究の目的
通産省工業技術院ではエネルギー・環境技術に関する大型プロジェクトを実施しています。効率的な研究開発プロジェクトの推進にあたってはプロジェクト立ち上げ前の可能な限り詳細な事前調査・研究が不可欠です。そこで先導研究ではプロジェクト化する前に技術的ブレークスルーや実用化した場合の経済性の見通し等について調査・研究を行います。
(2) 地中地盤蓄熱システム技術の概要
地球温暖化防止を目指した炭酸ガス排出抑制型社会への転換は、わが国の緊急課題となっています。夏季に発生する温排熱を貯蔵して冬季の暖房熱源に利用し、逆に冬季の冷熱を貯蔵して夏季の冷房熱源に利用することができれば、エネルギーの有効利用が図られ、省エネルギー、炭酸ガス削減にとって画期的な技術であるといえます。
これらの熱を有効に利用するためには、長期蓄熱用の大型施設を建設するだけの用地は都市部にはほとんど残っていないのが現状です。地上を生活や産業活動の空間として残しながら、残された未利用の深部地下空間を蓄熱に利用することが必要となります。
地中地盤蓄熱システムは、未利用地下の帯水層及び地盤の熱容量を利用し、地中と熱交換を行うもので炭酸ガス排出抑制型社会の構築に大きく貢献することが期待される技術です。
2.研究期間(平成11年10月〜13年3月)
・平成11年度:システムイメージ確立、課題抽出を行います。
・平成12年度:課題解決策、大プロ研究計画策定を行います。
3.研究実施体制
国研、大学、財団、様々な企業よりなる研究実施体制とし、また今後もできるだけ幅広い分野の企業の参画を頂いて研究を進めて行く予定です。
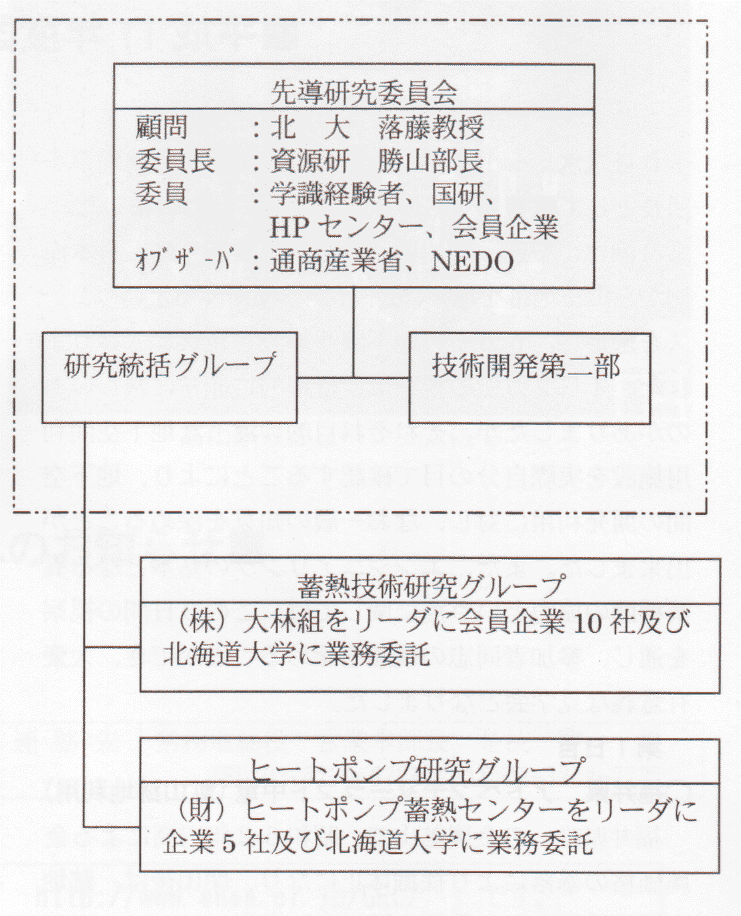
○地中地盤蓄熱システム海外調査
先導研究の一環として、この分野において世界の最先端をゆく米国にて調査を実施しました。 調査団は通産省工業技術院資源環境技術総合研究所の勝山部長(先導研究委員会委員長に就任頂いています。)を団長とし、総勢6名のエキスパートで構成されました。

調査参加者氏名(敬称略)及び会社名
勝山 邦久 工業技術院(団長)
山崎 起助 (財)ヒ−トポンプ蓄熱センター
安江 進 (株)大林組
香山 康晴 前田建設工業(株)
田中 俊博 ENAA
大木 太 ENAA
11月3日から14日に帰国するまでワシントンDC→アトランティックシティー(ニュージャージー州)→ワシントンDC→オクラホマシティー(オクラホマ州)→サンフランシスコとアメリカ大陸を横断するハードな旅で、国内地点間の移動にも1日がかりで、アメリカの広さを思い知らされた旅でした。
1.調査目的
地中地盤蓄熱は欧米において実用化が進んでいますが、技術的な中心課題であるボアホール削孔技術において最も進んでいる米国において実プラント調査、施工会社やメーカヒアリング、大学における研究状況調査を実施し、技術面、社会面、政策面等多面的な調査を行い、我が国に合った地中地盤蓄熱システム開発の参考とする事を目的とします。
2.調査内容
土壌熱源ヒートポンプ組合−GHPC、リチャードストックトン大学、オクラホマ州立大学−IGSHPA、オクラホマ州議事堂、リバーオークコミュニティーを訪問し、各所で意見交換、議論し、様々なデータや貴重な書類を入手することができました。
これを参考に我が国に合った地中地盤蓄熱システムの研究を進めてゆく予定です。 (技術開発第二部 大木 太 記)

■平成11年度国内見学会報告■
当センター恒例の行事である国内見学会が、11月10日(水)〜12日(金)の行程で山口専務理事を団長として総勢34名の参加によって行われました。
今回は、空路、石川県小松空港を皮切りに、日本海側から山岳地帯を越え、太平洋側へ横断するというコースを選定し、6カ所の地下関連施設を視察して参りました。1日2カ所の視察は、行程的に非常に厳しものがありましたが、それぞれ目的の違った地下空間利用施設を実際自分の目で確認することにより、地下空間の開発利用に対し、なお一層の知見を深めることが出来ました。また、エンジニアリングの基本となる異業種間の協力という点に関しては、この3日間の視察を通じ、参加者同志の親睦を深めることができ、大変有意義な見学会となりました。
第1日目
○福井県 アドベンチャーランド中竜(鉱山跡地利用)
福井県唯一の金属鉱山で、昭和62年円高による金
属価格の暴落により採掘休止になり、閉山後は、跡地を観光坑道として整備を行っています。
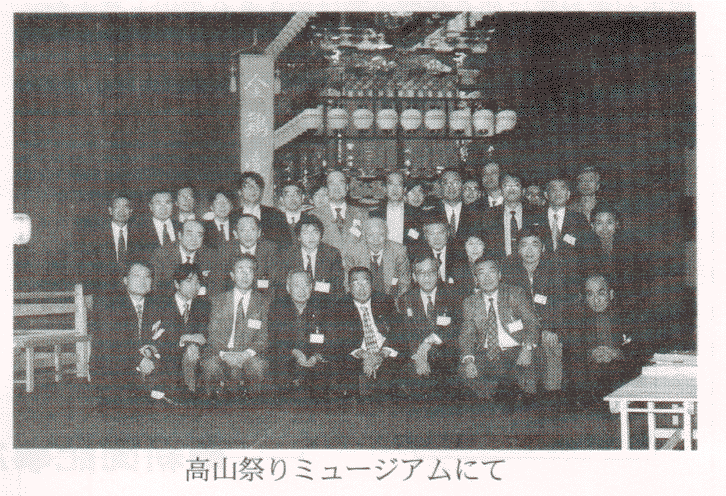 マイクロバスで、坑口(海抜630m)から、1800m(海抜510m)まで入坑し、徒歩にて坑内を見学しました。坑内では、採鉱掘現場で活躍した、大型機械類、坑内電車等が展示されています。坑内温度の一定を利用した、酒蔵設備や、ウドの栽培場もあり、地下湧水を利用したマスの養殖も行われています。 マイクロバスで、坑口(海抜630m)から、1800m(海抜510m)まで入坑し、徒歩にて坑内を見学しました。坑内では、採鉱掘現場で活躍した、大型機械類、坑内電車等が展示されています。坑内温度の一定を利用した、酒蔵設備や、ウドの栽培場もあり、地下湧水を利用したマスの養殖も行われています。
中竜鉱山では、上記の観光施設の他にも廃坑を利用して、福井市、大野市、立山市からの一般産業廃棄物(焼却灰)の処理を行っています。
〇岐阜県 高山祭りミュージアム(地中大空間)
地中空間は、美術品、特に木工品、漆器などの所蔵保管に悪影響を与える、紫外線、電磁波、放射能と、温度・湿度の変化を最小限に抑える効果があり、さらには、周囲の景観を損なうこともありません。この地中空間の特性を利用したのが、高山祭りミュージアムであり、豪華絢爛な祭り屋台、輪島塗金蒔絵、日本一の御輿、世界一の大太鼓、貴重な、美術工芸品が、展示され、参加者一同圧倒されました。
第2日目
○岐阜県 馬瀬川第一発電所
最初、岩屋ダムを見学しました。岩屋ダムは、飛騨川の支流馬瀬川に作られた、洪水調節、かんがい用水、水道用水、工業用水、発電の目的を持った多目的ダムで、中部電力で初めてのロックフィルダムです。
次に、馬瀬側発電所の見学を行いました。馬瀬川第一発電所は、ダム右岸側地下にあり、岩屋ダムを上池、馬瀬川第2ダムを下池とする揚水式発電所です。
当日、大型バスで、地下発電所内へ、直接乗り入れ、その規模の大きさに驚かされました。また、第一発電所に採用されている斜流形ポンプ水車は、1ユニット当たり容量14万9千㌔㍗で、斜流形ポンプ水車として、世界最大だそうです。また、主要な発電設備が、地下に納められているため、馬瀬川の、美しい景観が守られ、岩屋ダムのダム湖が、秋の紅葉に映えて静かなたたずまいを見せていたのが、印象的でした。
○岐阜県土岐市 東濃鉱山(地層科学研究)
東濃地科学センターは、岐阜県東濃地域の丘陵地に位置し、美濃焼の原料となる陶土や、美しい化石を産出する地層とウランを含む地層があり、地層との係わりの深い地域にあります。東濃鉱山は、日本最大の月吉ウラン鉱床を利用して研究のできる世界有数の施設です。まず最初、見学者全員、東濃地下学センターのあゆみとセンターの役割について説明を受けました。
東濃地科学センターでは、地下深部の地質環境を解明するため、地層科学研究を進めています。
説明後、地下−130mまで、鉱山用エレベーターで降り、広域地下水動研究の実験施設や、地層の状態、断層、鉱物等を見学することができました。なかでも、ウラン鉱床が、路頭している個所に紫外線をあて、青白く光っている鉱床を目にしたことは、圧巻でした。
第3日目
○岐阜県 根尾谷断層(震央断層)
濃尾地震は、1891年10月28日根尾谷を震央として、発生した直下型の大地震で、それに伴って生
じた地震断層は、延長距離(80km)や変位量(最大左横ずれ8m)が大きく、この地震のマグニチュードは、8.0と推定され、世界的にも大規模なものとして、注目を浴びています。
断層地下観察館では、根尾谷断層の垂直に断ち切ら
れた基盤岩石の6mにおよぶ食い違いの姿を目の前にするとき、一瞬にしてこのような大変動を生じた自然の威力に圧倒されました。
また、雨天のため、バスの中では東京大学名誉教授小島先生の臨時講義をいただきまして、参加者一同大変勉強になりました。
○愛知県 名城変電所(これからの変電所)
名城変電所は、名古屋城を取り囲む名城公園の正門前駐車場の地下空間を利用した新しい形の変電所です。
見学を終え、駐車場の前に立って見ますと、変電所上部の給気・排気塔や、エレベーター塔屋は、瓦屋根に、漆喰調の白壁や、石積みといった和風建築で仕上がっていて、名古屋城を含む周囲の景観のイメージに調和して、この足元の下に、超近代的な変電所があるとは信じられない思いでした。
最後に、今回の見学に際しまして、ご協力のいただきました関係者の方々に改めてお礼、感謝を申し上げます。 (技術開発第一部 安宅 洋 記)

■会員の皆様へのお知らせ■
○新規加入会員紹介
今回新たに新規加入された会員企業をご紹介します。
|
会 社 名 |
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 |
|
|
|
住 所 |
〒102-8220 東京都千代田区九 段北1-11-5 |
連 絡 先 |
常務取締役 営業本部長 是枝 慶一 殿 |
|
事業内容 |
地質調査、地盤解析、岩盤試験、物理探査 |
|
TEL;03-5276-6721 FAX;03-3262-7737 |


■「雪冷蓄熱システムの多目的利用に関する調査研究」の委員会活動状況報告■
「雪冷蓄熱システムの多目的利用に関する調査研究」は、「プロジェクト計画策定事業」の一つとして、本年度より2カ年の計画でスタート致しました。本研究のテーマである雪は、我が国の約50%を占める積雪地帯(2月の積雪深さ50cm以上)の都市においては、エネルギーと多大のコストをかけて処理する対象です。
そこで、この雪を資源としてとらえ、ビルや公園等の地下に貯蔵し、夏のオフィス等の冷房に供する事で、夏季の冷房需要に伴う電力需要のピークカットを行う事を考えました。利雪対策により、環境問題に寄与するのみならず、克雪に伴うコストの低減を目指し、このシステムを融雪槽等に多目的に利用する調査研究も行っています。
この調査研究の第2回委員会(委員長;北大 持田教授)が10月27日に北海道大学にて開催されました。
翌日、札幌市の協力を得て雪対策の現状調査を行いましたので、その概要を紹介致します。
札幌市は、年間降雪量4〜7mの豪雪地帯に位置する世界を代表する大都市です。都市機能を守るため札幌市が雪対策に使う年間金額は約150億円と莫大なものになっています。
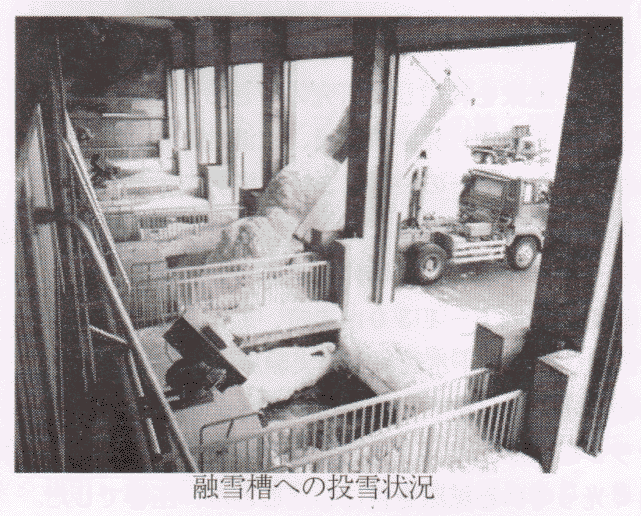 今回は雪対策のうち融雪槽の調査をおこないました。融雪槽は大きな水槽に下水処理水や温められた水を溜めて融雪する施設である。熱源としては、下水処理水や清掃工場の余熱、地域暖房の余熱など地域エネルギーを有効利用しています。今回調査を行った融雪施設は、都心北融雪槽と厚別融雪槽です。都心北融雪槽は、札幌駅北口広場総合整備事業の一環として地下駐車場や公共地下歩道と合わせて整備され冷暖房プラントの熱を利用して融雪が行われています。除雪作業は札幌駅から半径2kmが対象で年間、約24万m3の雪を融かしています。1日の融雪量は約4000m3で夜間に除雪作業がおこなわれ、トラック286台で融雪槽に運ばれ、40℃の温水で融雪される。 今回は雪対策のうち融雪槽の調査をおこないました。融雪槽は大きな水槽に下水処理水や温められた水を溜めて融雪する施設である。熱源としては、下水処理水や清掃工場の余熱、地域暖房の余熱など地域エネルギーを有効利用しています。今回調査を行った融雪施設は、都心北融雪槽と厚別融雪槽です。都心北融雪槽は、札幌駅北口広場総合整備事業の一環として地下駐車場や公共地下歩道と合わせて整備され冷暖房プラントの熱を利用して融雪が行われています。除雪作業は札幌駅から半径2kmが対象で年間、約24万m3の雪を融かしています。1日の融雪量は約4000m3で夜間に除雪作業がおこなわれ、トラック286台で融雪槽に運ばれ、40℃の温水で融雪される。
厚別融雪槽は下水処理場に隣接して整備され、約14℃の処理水の持つエネルギーで融雪を行っており、年間の雪の処理量は、約60万m3となっています。
本調査研究は、雪の持つ熱エネルギーの有効利用と計画施設の多目的利用が課題です。
札幌市の雪対策に関する今回の現状調査は大変参考になる貴重データとなりました。
(委員会事務局;竹中工務店 山本 光起 記)

■新聞記事からの紹介■
○社会資本整備に地下利用不可欠 −松山で研究会が講演会− ('99.11.6日付け 愛媛新聞 より)
地下の有効利用を検討する「地方の活性化をめざした地下空間利用研究会」(会長;稲田義紀愛媛大教授)の第十六回講演会が五日、松山市道後町の県民文化会館であった。
全国の研究者や企業、行政の担当者ら約百四十人が参加。稲田会長が「地下利用は確実に少しずつ動いている。活発な意見をいただき、新たな知見を得てもらいたい。」とあいさつした。
地下開発利用研究センターの山口健所長(エンジニアリング振興協会専務理事)が「地域の活性化と地下
利用」、大林組技術研究所の桑原徹主任研究員が「地下ダムを利用した水資源開発の現状」、大成機工の来馬章雄常務(元兵庫県都市整備局長)が「ライフラインの耐震対策」と題し、それぞれ講演した。
山口所長は「日本経済再生の起爆剤として地方が期待される」とし、「社会資本整備に地下利用が不可欠」と強調。利点として▽土地の高度利用▽地上景観の保全▽環境保全▽保温性、密閉性等地下特性▽防災面での活用−を挙げた。

|

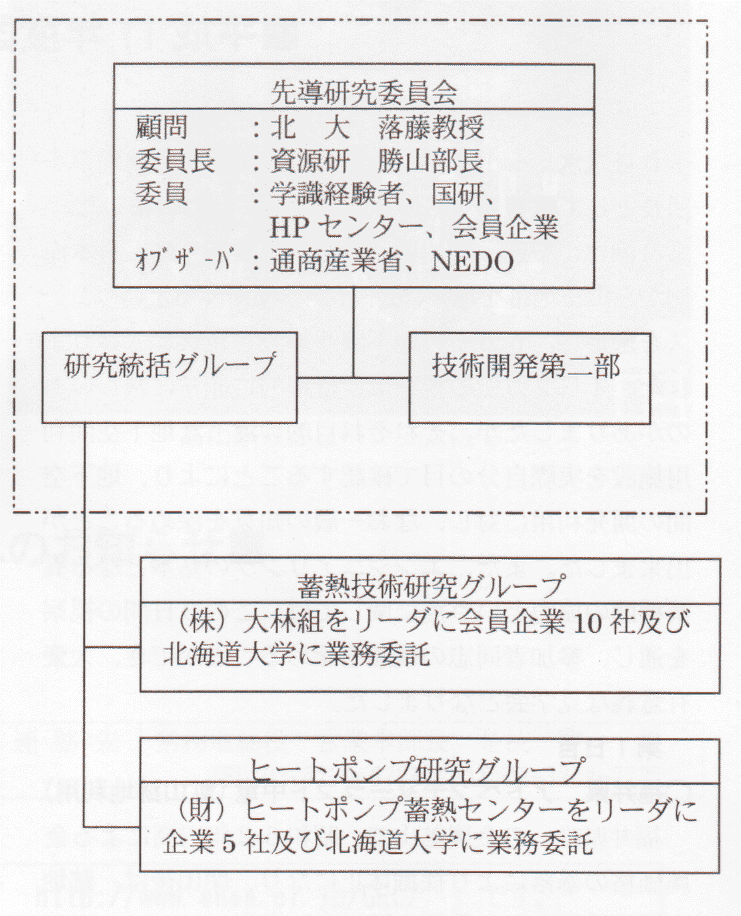

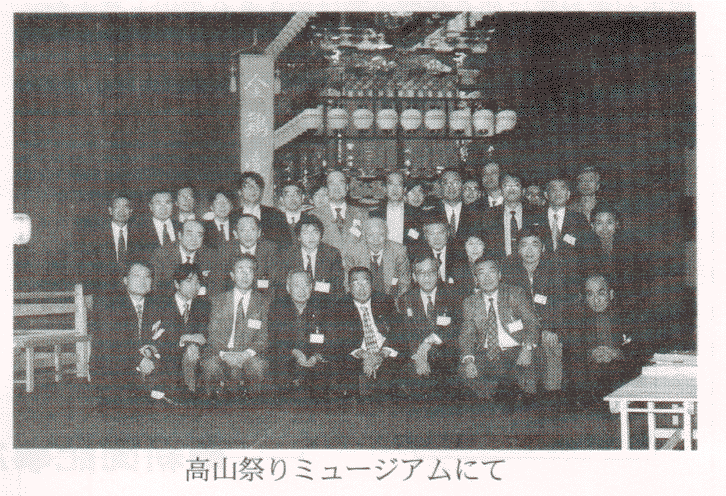 マイクロバスで、坑口(海抜630m)から、1800m(海抜510m)まで入坑し、徒歩にて坑内を見学しました。坑内では、採鉱掘現場で活躍した、大型機械類、坑内電車等が展示されています。坑内温度の一定を利用した、酒蔵設備や、ウドの栽培場もあり、地下湧水を利用したマスの養殖も行われています。
マイクロバスで、坑口(海抜630m)から、1800m(海抜510m)まで入坑し、徒歩にて坑内を見学しました。坑内では、採鉱掘現場で活躍した、大型機械類、坑内電車等が展示されています。坑内温度の一定を利用した、酒蔵設備や、ウドの栽培場もあり、地下湧水を利用したマスの養殖も行われています。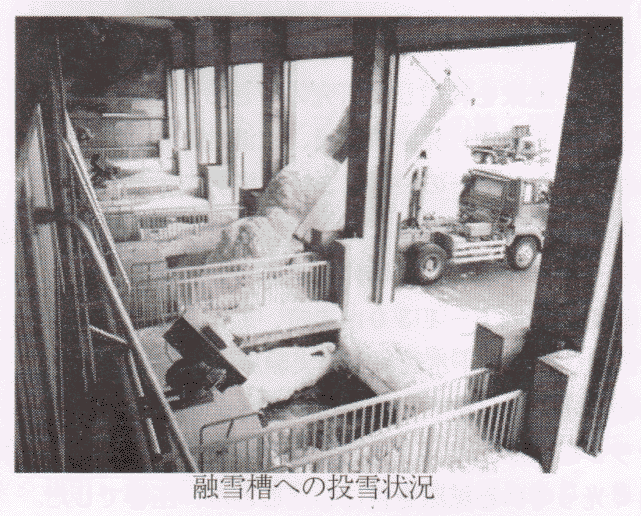 今回は雪対策のうち融雪槽の調査をおこないました。融雪槽は大きな水槽に下水処理水や温められた水を溜めて融雪する施設である。熱源としては、下水処理水や清掃工場の余熱、地域暖房の余熱など地域エネルギーを有効利用しています。今回調査を行った融雪施設は、都心北融雪槽と厚別融雪槽です。都心北融雪槽は、札幌駅北口広場総合整備事業の一環として地下駐車場や公共地下歩道と合わせて整備され冷暖房プラントの熱を利用して融雪が行われています。除雪作業は札幌駅から半径2kmが対象で年間、約24万m3の雪を融かしています。1日の融雪量は約4000m3で夜間に除雪作業がおこなわれ、トラック286台で融雪槽に運ばれ、40℃の温水で融雪される。
今回は雪対策のうち融雪槽の調査をおこないました。融雪槽は大きな水槽に下水処理水や温められた水を溜めて融雪する施設である。熱源としては、下水処理水や清掃工場の余熱、地域暖房の余熱など地域エネルギーを有効利用しています。今回調査を行った融雪施設は、都心北融雪槽と厚別融雪槽です。都心北融雪槽は、札幌駅北口広場総合整備事業の一環として地下駐車場や公共地下歩道と合わせて整備され冷暖房プラントの熱を利用して融雪が行われています。除雪作業は札幌駅から半径2kmが対象で年間、約24万m3の雪を融かしています。1日の融雪量は約4000m3で夜間に除雪作業がおこなわれ、トラック286台で融雪槽に運ばれ、40℃の温水で融雪される。