|

第128号/2000.5
■齋藤会長退任・増田新会長選任
■第43回定例理事会開催
■大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案
■平成12年度新部会参加募集のご案内
■会員の皆様へのお知らせ
■退任メンバーの紹介
■齋藤会長退任・増田新会長選任■
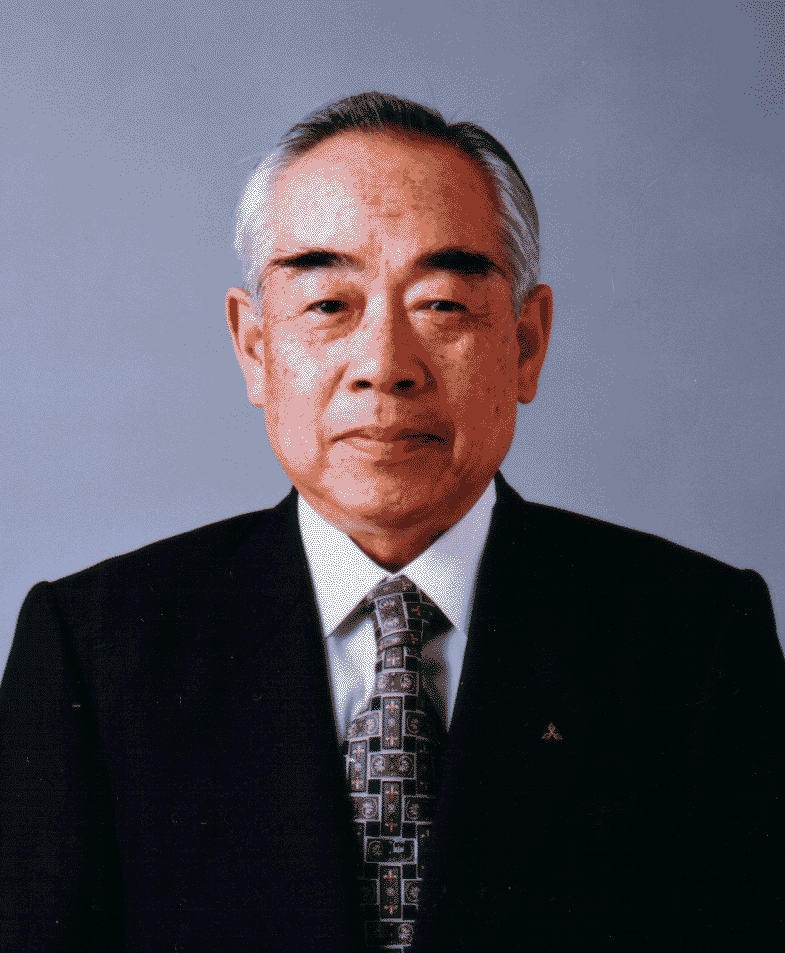 平成9年4月より3年間にわたり当エンジニアリング振興協会会長職をお務めいただいた齋藤裕氏((社)経済団体連合会顧問)は、このたび退任されることとなりました。 平成9年4月より3年間にわたり当エンジニアリング振興協会会長職をお務めいただいた齋藤裕氏((社)経済団体連合会顧問)は、このたび退任されることとなりました。
その後任として、平成4年7月から平成7年6月まで当協会の理事、運営委員会委員を務められ、かねてより協会の事業活動に関し多大のご指導ご貢献をいただいております、増田信行氏(三菱重工業㈱取締役会長)が、3月29日開催の理事会において会長に選任されました。
増田新会長のもとで力を合わせ、エンジニアリング業界の更なる発展に尽くしてまいりたいと存じますので、会員各位の一層のご支援ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
■第43回定例理事会開催■
3月29日(水)午後3時30分から当協会において、通商産業省機械情報産業局産業機械課課長補佐の森下泰氏を来賓にお迎えして開催されました。
議題は次のとおりで、いずれも原案のとおり承認されました。
第1号議案 平成12年度事業計画(案)および収支予算(案)について
第2号議案 会長、理事長および専務理事の選任ならびに事務局長の委嘱について
①会長について
斉藤裕氏の退任に伴い、三菱重工業㈱取締役会長の増田信行氏にお願いしたい旨の提案があり、満場一致で承認されました。
②理事長、専務理事について
現理事長の園田保男氏、現専務理事の戸倉修氏、山口健氏に引き続きお願いすることが承認されました。
③事務局長の委嘱について
引き続き飯倉常務理事に委嘱することが承認されました。
第3号議案 評議員の委嘱について41名の候補者に委嘱することが承認されました。
第4号議案 顧問の推薦について9名(再任8名、新任1名)を推薦することが承認されました。

■大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案■
国土庁 大都市圏整備局計画課 大深度地下利用企画室
1.背景・経緯
我が国の大都市地域において社会資本を整備する場には、土地利用の高度化・複雑化が進んでいること等から、地上で実施することは困難を増す傾向にある。
一方、社会資本整備のための用地を取得するには、地権者との交渉・合意を経て権利を取得することが基本であるが、その際、地権者との権利調整に要する時間が総じて長期化する傾向にあり、効率的な事業の実施が困難となっている。
これらの理由から、大都市地域における社会資本整備には、主に道路等の地下が利用されているが、この場合にも、合理的なルートの設定が困難となりがちであり、また、道路の地下を中心に、浅い地下の利用は輻輳している。
このため、地上及び浅深度地下に加えて、「地権者等による通常の利用が行われない地下空間」である大深度地下を、国民の権利保護に留意しつつ、社会資本の整備空間として円滑に利用するための制度を導入する必要性が高まっている。
このような状況を踏まえ、平成7年8月に施行された臨時大深度地下利用調査会設置法に基づき、臨時大深度地下利用調査会が設置され、3年間にわたり技術・安全・環境及び法制の各面から慎重な検討が行われた結果、平成10年5月、内閣総理大臣に答申が行われ、直ちに国会に対して報告された。
本法案は、この答申を踏まえ、公共の利益となる一定の事業に係る大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、これらの事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用図るための法的枠組みを整備するものである。
2.法案の概要
(1) 大深度地下の定義
次に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さの地下・地下室の建設のための利用が通常行われない深さ (地下40m以深)
・建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持層上面から10m以深)
(2) 対象地域及び対象事業
・人口の集中度等を勘案して政令で定める地域 (三大都市圏等)
・道路、河川、鉄道、通信、電気、ガス、上下水道等の公益性を有する事業その他政令で定める事業
(3) 適正かつ合理的な利用の確保
大深度地下の適正かつ合理的な利用を確保するため、大深度地下使用基本方針、大深度地下使用協議会、 事前の事業間調整等について定める。
(4) 大深度地下の使用権の設定
事業者の申請に基づき、国土交通大臣(広域的な事業等の場合)又は都道府県知事(その他の事業の場合)
が使用権の設定を行う。なお、国土交通大臣に対する申請は、事業所管大臣を経由して行う。
(5) 使用権の設定に伴う補償
大深度地下に使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しないと推定されるため、事前に補償を行うことなく使用権を設定する。例外的に補償を要する場合は、使用権設定後、土地所有者等から事業者にして請求を行う。
(6) 法案の施行時期
本法案は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
3.国会における審議の状況
・衆議院においては、平成12年3月29日の建設委
員会、30日の本会議のそれぞれにおいて、賛成多数により可決。
・今後、参議院(国土・環境委員会)での審議を経て、現在開会中の第147回国会での成立を目指している。 (平成12年4月25日現在)
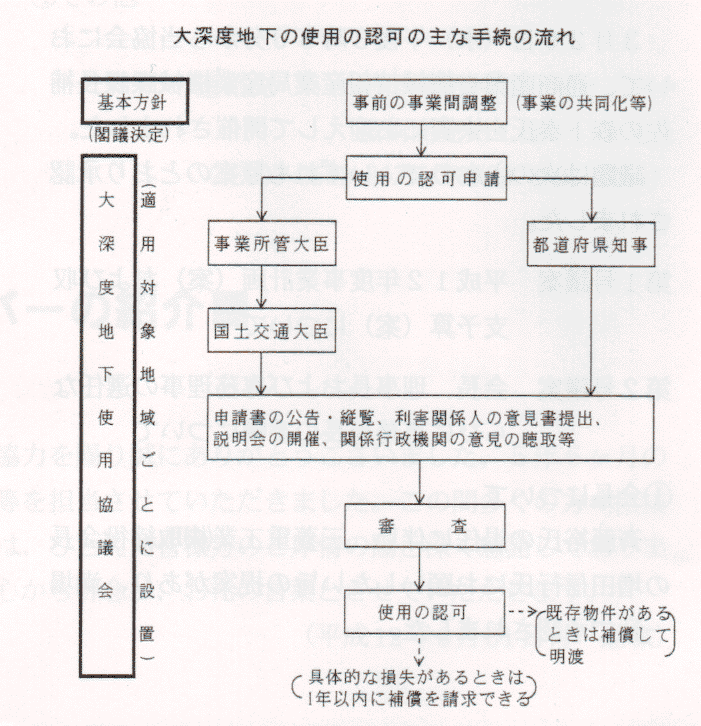

■平成12年度新部会参加募集のご案内■
既に賛助会員連絡担当者会議においてご説明申上げたとおり、運営会議の議決により平成12年度より下記の地下利用推進部会活動を発足させるべく、賛助会員企業の連絡担当者殿宛に委員参加の募集をお送りしております。改めてこの概要をご紹介します。
1.地下利用推進部会
平成10年度~12年度の地下利用推進部会は、3専門部会(地下利用促進専門部会、都市構築専門部会、地域プロジェクト専門部会)の構成により調査研究を進め、当初の予定を超えて大きな成果が得られました。
また、本年3月以来、社会資本整備のために「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案」が国会で審議されており、新たな大深度地下事業に弾みがつくことが期待されます。また産業技術戦略等の動きにより、高齢化、情報化、環境市場など新たな雇用を生み出す新規・成長分野への期待が高まっています。今後予想される地下空間利用の動向とニーズの変化に沿って、活動フレームを以下の通り改編し発足致します。
2.改編のねらい
会員企業に常に開かれた組織とし、参加目的の多様化に沿うものとして会員企業が興味のある分野で、新しい地下利用の形態やニーズを探索し、参加委員の技術ポテンシャルの向上を図り、地下開発利用の普及を図ることをねらいとして、
① 参加企業もしくは業界に有益な方向の活動をめざす。
② 地下利用の普及促進に資する方向をねらう。
③ 参加委員が何らかの成果もしくは経験を持ち帰れるものとすること。
④ 将来のプロジェクトや受託など成果の出やすい受け皿を用意すること。
を目的とします。
(1)募集分野とその組織
1)募集分野
①地下利用事業性専門部会 (仮称)
地下利用の理念、地下利用の助成制度と規制、地下利用評価等の地下利用促進策を研究します。
②都市ネットワーク専門部会 (仮称)
都市のエネルギー自立性、広域熱供給システム等新たな社会ニーズに対応する都市の新しいネットワークを対象範囲とします。
③都市生活専門部会 (仮称)
生活、供給処理系、情報処理、運輸拠点など高齢化や情報化の変化に向けて新しい地下利用を探ります。
④地下特性活用専門部会 (仮称)
地下の恒温性、恒湿性、不燃性、振動遮断性防爆性、電波遮断性など、特に省エネルギーや、エネルギー合理化に有効なこれからの地下を可能性を研究します。
⑤環境産業専門部会 (仮称)
炭酸ガス処理及び循環、廃棄物、リサイクル、地下水循環など新たな環境の産業化の分野を対象とします。
2)組織
・ 各専門部会は、10~20名程度とします。
分野毎の参加希望を尊重することとします。このため、募集の結果によって専門部会枠組の修正があり得るものとします。
・ 各専門部会には、部会長・副部会長、各1名を置きます。
・ 各専門部会は、必要に応じてテーマごとのグループが編成できることとします。
地下利用推進部会活動の企画、運営及び各部会相互連絡のための幹事会を設けます。
(2)基本方針
1)各部会の活動方針と具体的活動内容は、各部会にて検討の上決定されます。
2)中長期的な視野で早急に取り組むべき重点課題を考慮し自主研究に計画的に取り組みます。
3)研究結果と活動経緯を報告書に取りまとめます。活動期間を2年間程度とし、必要に応じて見直します。
(3)今後の予定
1)委員の募集期限: 5月19日まで
2)各部会の編成 : 5月下旬
3)各部会の発足 : 6月下旬
(4)問合せ先
「新部会参加募集」についての担当窓口
当センター技術開発第一部 寺野
(TEL:03-3052-3671/FAX:03-3502-3265)

■会員の皆様へのお知らせ■
○第223回サロン・ド・エナ開催のご案内
日 時 :平成12年5月17日(水)17:30~(於:当協会6階CDE会議室)
講 師 :三羽 宏明 氏(日本下水道事業団 技術開発部 総括主任研究員)
テーマ :「下水汚泥処理・有効利用の動向」
講演要旨: 下水道は川、湖沼、海域の水環境改善の要として重点的な整備普及に取り組んだ結果、平成10年度末の人口普及率は58%に達している。しかし、普及拡大につれその汚泥発生量は増加し、汚泥処理工程での減量化や汚泥の有効利用の技術開発が幅広く取り組まれている。この結果、普及率の増加にもかかわらずここ十年の発生汚泥の伸びは横ばい状態が保たれ、また、有効利用率も45%にまで向上し埋め立て処分量は低減している。これら減量化・有効利用の手法、技術の概要について、様々な事例をまじえて紹介する。
申込要領:FAXで事務局へお申し込み下さい。申込多数の場合は先着順で締め切らせていただきます。
地下開発利用研究センター 事務局 中村
(TEL:03-3502-3671/FAX:03-3502-3265)
○平成11年度新規産業創造型提案募集事業成果報告会開催
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の平成11年度新規産業創造型提案公募受託事業成果報告会が、3月14日(火)~15日(水)東京ビックサイトに於いて開催され、当センターと会員企業の受託成果として、以下の2件が報告されました。
Ⅰ.「高炉スラグ有効利用による最終処分場遮水システムの開発」
Ⅱ.「下水処理場等から発生する未利用ガスを利用する低NOxガスタービン燃焼技術の開発」
上記2テーマも会員企業の皆様からのご提案とご相談をもとに研究開発事業が実施されました。
当センターでは、地下もしくは半地下、覆土式地下の利用、地中地盤の利用、ならびに地下の種々の課題を含めて、下記の分野について、会員企業皆様から随時、テーマ提案もしくはアイデアのインプットをお願いしています。どんなことでも結構ですので、ご連絡をお待ちしております。
①未利用エネルギー・省エネルギー関連分野
②環境関連分野(廃棄物・リサイクル、地球温暖化対策、有害物質管理システムなど)
③都市環境整備関連分野(空間の有効利用、経済・生活基盤、流通システムなど)
④その他
連絡先 : 地下開発利用研究センター 技術開発第一部 安宅
(TEL03-3502-3671/FAX03-3502-3265)

■退任メンバーの紹介■
北風 宏(前備蓄プロジェクト室 技術顧問)
地下開発利用研究センター在職中は皆様のご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございました。5年6ヶ月の期間、石油ガス備蓄基地建設に係わる基本計画調査業務等を担当させていただきました。この間多くの方々に接する機会に恵まれ、大過なく業務を遂行できましたことは、ひとえに皆様方のご厚情の賜と深く感謝しております。最後に皆様のご健勝と地下センターの益々の発展を心から祈念し、お礼の言葉とさせていただきます。
(平成12年3月31日付 退職)

|