|

第133号/2000.10
■制御ボーリング技術開発の紹介
■石油ガス国家備蓄基地詳細・基本計画調査(その2)
■エンジニアリングシンポジウム2000開催のご案内
■会員の皆様へのお知らせ
■新聞記事からの紹介
■制御ボーリング技術開発の紹介■
当センターが、(財)産業創造研究所より受託し、技術開発を行っている"制御ボーリング技術"について紹介します。
1.はじめに
産業創造研究所では、平成10年度から通商産業省の委託を受け、沿岸地域の地下水環境を把握することを目的とした「地下水流動調査」を実施しています。その一環として、海底下の地下水環境を把握するための陸上からのボーリング技術として制御ボーリングに関する技術開発を行っています。
2.制御ボーリング技術
これまでの岩盤調査におけるボーリング技術は、垂直孔もしくは傾斜孔よって行われてきました。この手法では、水平方向に広がる調査対象岩盤の評価などに対して効率が良くありませんでした。
制御ボーリング技術は、岩盤評価対象地域に向けて傾斜孔を掘削し、その先の評価対象地域で水平に方向を修正し掘削する技術です。
3.制御ボーリング技術に関する技術開発
この掘削技術は、これまでに硬岩を対象とした岩盤調査に用いられ、適用性が検証されていますが、より岩盤強度の低い軟岩への適用性について技術開発を行っております。
昨年度は、ボーリング孔を偏心させるために重要なツールの設計・製作を行いました。
そのほか硬岩の掘削に適用するためのビットの検討、掘削泥水の検討などを行いました。
今年度は、昨年度の検討結果を基に掘削装置の試作機を作成し、実際に硬岩を掘削し、適用性について検討を行う予定です。
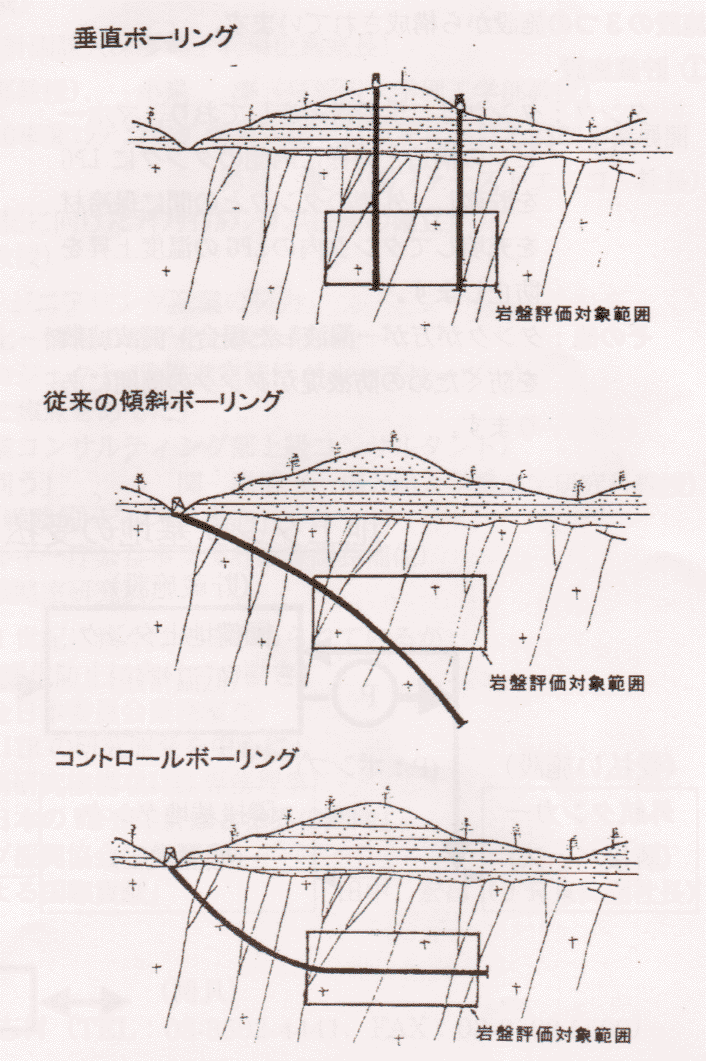

■石油ガス国家備蓄基地詳細・基本計画調査(その2)■
前号で紹介した石油ガス国家備蓄の内、地上タンク方式の基地について説明します。
石川県七尾・長崎県福島・茨城県神栖の3地点は、地上タンク方式を採用しています。液化石油ガス(以下LPGという)は石油に比較し温度と圧力の関係が顕著で低温常圧状態から温度が上がると圧力が上がります。このLPGの性質を利用してタンク方式の選定が行われます。
地上タンク方式では低温常圧の状態でLPGを貯蔵する平底円筒式二重殻タンクと常温高圧の状態で貯蔵する球形タンクがあり、球形タンクは設計圧力が高く大型化は不可能で大量の貯蔵には低温常圧の二重殻タンクが適しています。円筒式二重殻タンク一基当たりの容量は5万トンで、基数は七尾基地に5基、福島基地に4基、神栖地点は現在計画中です。
タンクの諸元は別表に示すようにタンク内径は59m、設計温度はプロパン-45℃、ブタン-10℃となっています。ご存知のようにプロパンは家庭用、ブタンはタクシー等に利用されています。
地上基地は大別すると貯蔵施設、運営施設、受払い施設の3つの施設から構成されています。
① 貯蔵施設
タンク:タンクは二重殻構造をしており、マホービンの構造と同様に内側のタンクにLPGを貯蔵し、外側のタンクとの間に保冷材を充填してタンク内のLPGの温度上昇を防止します。
その他:タンクが万が一漏液した場合、漏液拡散を防ぐための防液堤がタンクの周囲にあります。
② 運営施設
LPGを安全に貯蔵するための施設として、気化したガスを再液化するためのBOG処理設備、電気計装・安全防災その他の設備があります。
③ 受払い施設
大半のLPGはサウジアラビアを始め主に中東から低温で輸入されます。受払いには、今回の計画では隣接する既存の受払い施設を利用します。払出しは低温常圧でも常温高圧でも可能です。但し常温高圧の場合は隣接基地のヒーター等の設備を利用します。
備蓄基地の日常は、LPGを安全に貯蔵し、緊急払出しに即刻対応できるように、ポンプ・計器等の整備をしておくことになりますが、当然、緊急時の安定供給を満足出来るような払出し設備の能力が重要となります。また、兵庫県南部地震以降、耐震設計基準が見直され、各地点とも最新の設計基準で調査・設計が行われているところです。
|
項 目
|
諸 元 (七尾基地の例)
|
|
プロパン低温タンク
|
ブタン低温タンク
|
|
形 式 |
平底円筒式二重殻タンク
|
|
容 量 |
5万トン
|
5万トン
|
|
設計条件 |
内 槽
|
外 槽
|
内 槽
|
外 槽
|
|
設計温度 |
- 45℃
|
常 温
|
- 10℃
|
常 温
|
|
液 比 重
|
0.588
|
0.601
|
|
内 径
|
59.0m
|
60.3m
|
59.0m
|
60.3m
|
|
高 さ
|
43.7m
|
44.8m
|
42.9m
|
44.1m
|
|
最高液位
|
31.20m
|
30.51m
|
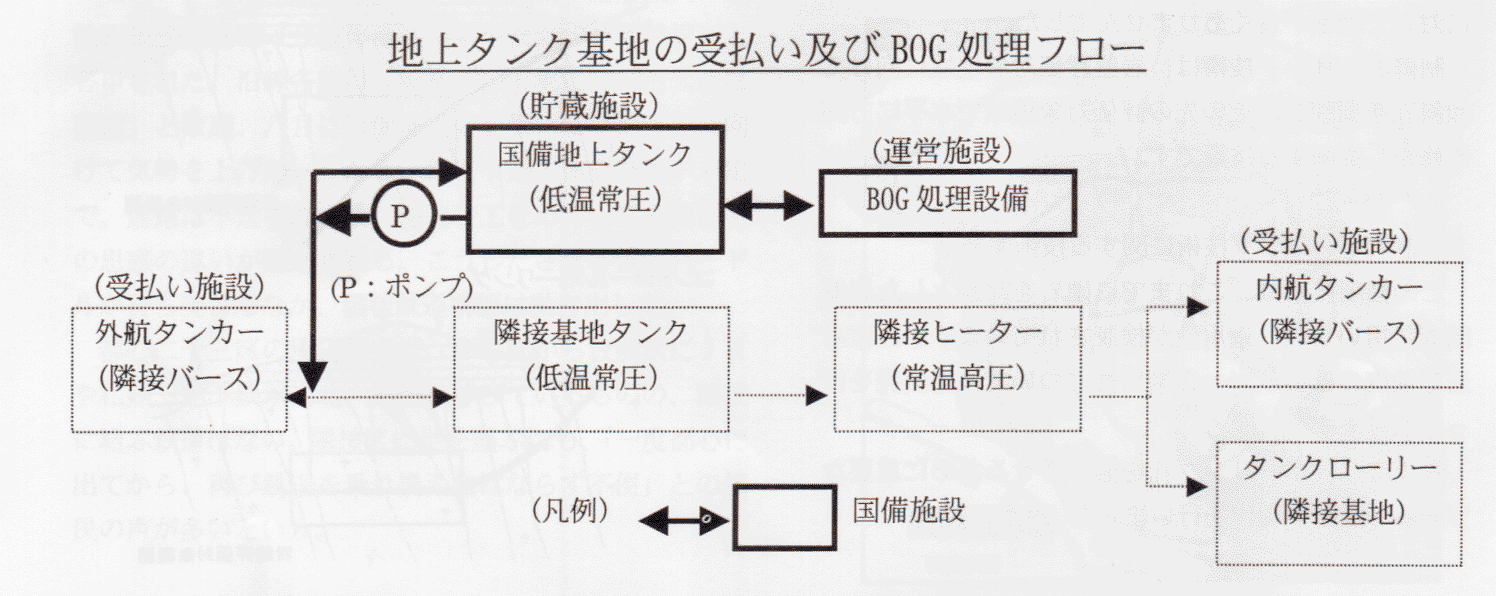

■エンジニアリングシンポジウム2000開催のご案内■
*日 時 ;平成12年 11月15日(水)10:00~17:30 、16日(木)9:30~19:00
*場 所 ;大手町サンケイプラザ(旧サンケイ会館)
*申込方法;「参加登録書」に必要事項をご記入の上、郵送あるいはFAXにてお早めにお申し込み下さい。
今回よりホームページ(http://www.enaa.or.jp/)のトピックス欄にてお申し込みもできます。
*申込期限;平成12年 10月25日(水)
*参加費 ;シンポジウム&交流会:15,750円 (消費税込み)
*統一テーマ;ニュー・ミレニアムを切り拓く-エンジニアリングの挑戦!
|
15日 4F ホール |
|
10:00~12:00 |
「経営が企業を変える-"エンジニアリングの挑戦!"に寄せて」
八城 政基(新生銀行㈱会長兼社長) |
|
13:00~15:30 |
「21世紀のエンジニアリング産業のあり方」(パネルディスカッショ)
コーディネータ:野中 郁次郎(一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)
パネリスト :唐津 一(東海大学開発技術研究所教授)
玉田 樹(㈱野村総合研究所創発センター長)
寺島 実郎(㈱三井物産戦略研究所所長)
中藤 信(石川島播磨重工業㈱常任顧問) |
|
16:00~17:30 |
「"製造業が国を救う"からのメッセージ」
エーモン・フィングルトン(経済ジャーナリスト) |
|
15日 3F 会場 併催行事(但し招待者のみ) |
|
17:30~18:00 |
功労者表彰式 |
|
18:00~19:30 |
親睦パーティー |
|
16日 3F A会場 「21世紀に向けてのエンジニアリング産業のチャレンジ」 |
|
9:30~12:30 |
「21世紀における大深度地下開発への挑戦」
本東 信(国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室長)
花村 哲也(岡山大学環境理工学部教授)
小泉 淳(早稲田大学理工学部教授) |
|
13:30~15:00 |
「わが国における省エネルギーへの期待とESCO事業エンジニアリング将来展望
-21世紀におけるESCO事業展開とエンジニアリング業界への期待」 筒見 憲三(㈱ファーストエスコ 社長) |
|
15:30~17:00 |
「メンテナンス時代におけるエンジニアリング-21世紀に向けたライフサイクルメンテナンス技術の確立」
高田 祥三(早稲田大学理工学部教授) |
|
16日 3F B会場 「当面の苦境を乗り切るためのエンジニアリング産業の努力」 |
|
9:30~11:00 |
「プロジェクト・エンジニアリングの進化-情報の電子化と統合化」
増川 順一(千代田化工建設㈱プロジェクトIT推進室統括グループリーダー) |
|
11:00~12:30 |
「プラント産業と国際競争力-電力産業に焦点をあてた」
松本 哲 (㈱野村総合研究所産業コンサルティング部上級コンサルタント) |
|
13:30~15:00 |
「エンジニアリング産業とアジア戦略を問う」
関 満博(一橋大学大学院商学研究科教授) |
|
15:30~17:00 |
「エネルギーインフラ事業の規制緩和と(戦略的)ビジネス動向」
新川 達也(通商産業省資源エネルギー庁公益事業部計画課課長補佐)
小田 正規(㈱三和総合研究所新戦略室研究員) |
|
16日 3F C会場 「エンジニアリング産業の貢献、21世紀に我々は何を求められているか」 |
|
9:30~11:00 |
「世界自然保護基金(WWF)から見た地球温暖化防止に向けての動き」
中村 圭一((財)世界自然保護基金日本委員会業務室長) |
|
11:00~12:30 |
「グリーンバイオ革命と地球環境対策-RITEの研究開発を中心に」
山口 務 ((財)地球環境産業技術研究機構(RITE)専務理事) |
|
13:30~15:00 |
「水素利用技術開発の現状と将来展望-日本のWE-NET計画と世界の動向」
岡野 一清((財)エンジニアリング振興協会研究理事) |
|
15:30~17:00 |
「新幹線技術の海外展開-最先端技術による国際貢献」
田中 宏昌(JR東海副社長) |
|
16日 4F ホール |
|
17:15~19:00 |
交流会 |
*申込・問合先;シンポジウム事務局 上原/伊藤/志村
(TEL:03-3502-4441、FAX:03-3502-5500)

■会員の皆様へのお知らせ■
○第227回サロン・ド・エナ開催のご案内
日 時 : 平成12年10月18日(水)17:30~(於:当協会6階CDE会議室)
講 師 : 輪島 実樹 殿(社団法人ロシア東欧貿易会ロシア東欧経済研究所 研究員)
テーマ : 「カスピ海地域における石油・天然ガス開発・輸送の動向と日本の関わり」
講演要旨:
最近、カスピ海北部のカザフスタンで大規模油田の発見が発表された。これには日本企業も参加しており、この地域の石油・天然ガス開発の動向及びその輸送ルートの確保に注目が集まっている。
こうした最近の状況を踏まえ、今後この地域の開発が、オイルメジャーの動向と共に、我が国にどのような影響を及ぼすのかについて、ロシア東欧貿易会で中央アジアを含む旧ソ連圏のエネルギー開発についての多くの記事を書かれている輪島実樹先生に言及していただく。
申込要領: 参加される方の①フルネーム ②所属役職 ③連絡先 を事務局へお申し込み下さい。
申込多数の場合は先着順で締め切らせていただきます。
地下開発利用研究センター 事務局 中村
(TEL:03-3502-3671/FAX:03-3502-3265)
(mail:hiromi@enaa.or.jp)
○「地方の活性化をめざした地下空間利用研究会」講演会のご紹介
日 時 : 平成12年11月 2日(木)13:00~17:00
場 所 : 愛媛県県民文化会館(愛媛県松山市道後町二丁目5-1)
内 容 :①「地下式下水処理場の計画と建設について」
下水道事業団 工務部技術管理課長 木全 隆 氏
②「放射性廃棄物の地下貯蔵・地層処分」
愛媛大学 工学部環境建設工学科 教授 矢田部 龍一 氏
③「最近のトンネル・地下空洞建設技術について」
鹿島建設㈱ 技術研究所 土木技術研究部 主任研究員 山本 拓治 氏
連絡先 : 愛媛大学工学部環境建設工学科岩盤工学研究室
(TEL:089-927-9823・9842/FAX:089-927-9842)

■新聞記事からの紹介■
○「環状鉄道網」進路は不透明-エイトライナー・メトロセブン構想-
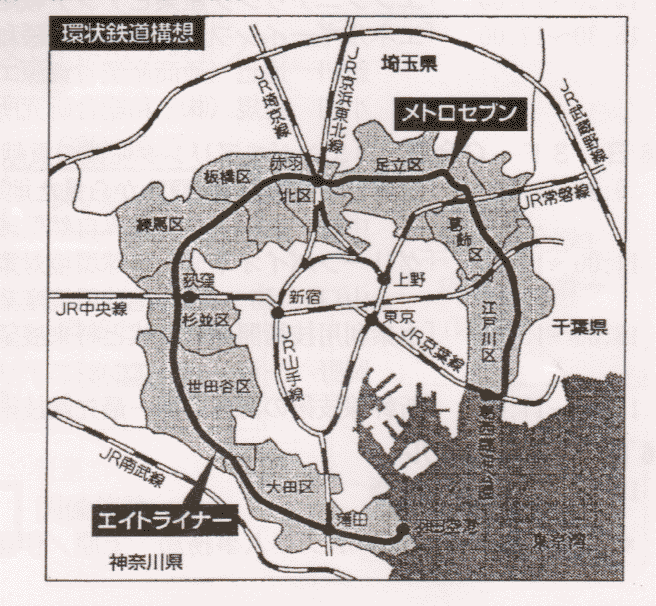 (2000.9.18日付 産経新聞より) (2000.9.18日付 産経新聞より)
都心の周辺部を環状に結ぶ道路網の環状7号、8号の地下を鉄道網でも結ぼうとする「エイトライナー・メトロセブン」の構想が今年一月、運輸大臣の諮問機関の運輸政策審議会で「今後整備について検討すべき路線」と答申された。沿線各区は「両構想の実現に向けた大きな前進」と歓迎、八月には促進大会を開いて早期実現に向けて気勢を上げた。
しかし、鉄道事業主体や財源が未定で、進路は不透明なまま。優先着工をめぐっても関係者の思惑の違いが懸念される。こうしたさまざまなハードルが待ち受けるなか、環状鉄道構想は動き出した。
都心二十三区の周辺部では、中心部から放射状にJRや私鉄、地下鉄が南北、東西に伸びているものの、環状に結ぶ鉄道はない。隣接区に足を運ぶにも、「一度都心に出てから、再び鉄道を乗り換えねばならず不便」との都民の声が多いという。
エイトライナー・メトロセブン構想は、こうした交通過疎をカバーするため、都心周辺部の各区を環状の鉄道網で結ぼうとする計画だ。

|
