|

第134号/2000.12
■研究企画委員会報告
■センター運営会議報告
■第20回エンジニアリング功労者賞受賞者紹介
■地下利用推進部会活動報告
■会員の皆様へのお知らせ
■新聞記事からの紹介
■研究企画委員会報告■
平成12年度の第2回研究企画委員会が、10月5日(木)午前10時00分より当協会6階会議室において開催されました。
山口専務理事より開会挨拶と、新委員の紹介がなされた後、高野委員長の司会により議事が進められました。また、議事に先立ち、通商産業省 環境立地局小林課長補佐殿より来賓の挨拶を戴きました。
議題と議事内容の概要は以下の通りです。
議題1:平成13年度補助金要望について
平成13年度の機械工業振興資金要望(暫定案)が説明され承認されました。
議題2:平成12年度事業進捗状況について
本年度上半期の社会開発システム策定事業、社会開発プロジェクト計画策定事業の進捗状況の報告があり、
いずれも順調に進行していること、更に、第4期地下利用推進部会の初年度の各部会活動が報告され、部会の基本的活動方針が紹介されました。
また、地下情報推進部会、受託事業活動、自主事業活動についての進捗状況の報告と説明があり、いずれも承認されました。
議題3:平成13年度活動テーマについて
平成13年度のテーマ募集に関し、今年度のテーマ募集の改訂についての説明及びその改訂結果の報告が
ありました。また研究企画ワーキンググループの検討結果を含め、各テーマについての説明がありました。
全提案件数17テーマの内委員会テーマとして5テーマ、プロジェクトテーマとして4テーマ候補に挙げ、そのうち平成13年度テーマとして、委員会テーマ2テーマ、プロジェクトテーマ2テーマを新規テーマとして取り上げる見込みにしており、その内容と優先順位について各委員との意見交換行われた後審議が行われました。審議の結果原案通りの優先順位をもとにして、新規テーマ候補とする事、また、上位のテーマに不都合が発生した場合は、順次繰り上げ当選となることで承認されました。
議題4:その他
その他,GEC行事報告として、成果発表会とサロンドエナの報告、並びに国内見学会の案内、及びエンジニアリングシンポジウム'2000の案内が紹介されました。
尚、新委員の方は下表の通りです。 (敬称略)
|
職 務
|
社 名
|
氏 名
|
所 属
|
|
委 員 |
富士電機㈱ |
横山 武夫 |
情報システム事業部社会システム部参与 |
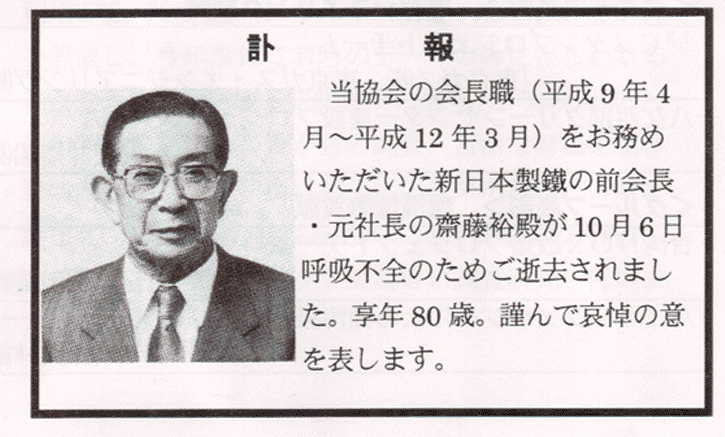

■センター運営会議報告■
平成12年度の第2回センター運営会議が、10月12日(木)午前10時より当協会6階会議室において開催されました。山口専務理事より挨拶及び新委員の紹介がなされた後、望月委員長の司会により議事が進められました。また、開会にあたり、来賓を代表して、本年7月、通商産業省 環境立地局 産業施設課 平野課長殿の後任となられた細川課長殿より自己紹介を兼ねて以下のようなご挨拶を戴きました。
「公共事業を巡り、現在大変大きな動きが3つあり、第1は、公共事業の中止。第2は、フルプラン7つの大きな水系に関しての水資源開発基本計画を10年ぶりに改訂する。第3は、PFI民間資本による社会基盤の整備。こういう動きは、公共と非公共の境界、官と民の境界をどこに持っていくか、どういう風に動かしていくかという意味で大きな潮流となっている。地下空間利用促進という観点からもこうした動きが追い風となるように注視しながら対応していく必要がある。
本年5月、地下空間利用に関する法律が成立し、来年5月には、新しい法律のもとで、地下空間の利用が大いに進んでいくことが期待されているので、地下センター及び運営会議のメンバーの皆様には、地下空間の利用が進むよう引き続き英知を結集されて尽力を戴きたい。」
当日の会議では、研究企画委員会での審議結果に基付き、以下の議題について審議及び報告がなされ、いずれも承認・了承されました。
議題1:平成13年度補助金要望について
議題2:平成12年度事業進捗状況について
議題3:平成13年度活動テーマについて
議題4:その他
尚、センター運営会議の新役員の方は下表の通り。
(敬称略・順位不同)
|
職務
|
会社
|
氏名
|
役職
|
|
委 員
|
東京ガス㈱ |
高砂 智之
|
専務取締役 |
|
〃
|
㈱日立製作所 |
久野 勝邦
|
専務取締役 |
|
〃
|
三井海上火災保険㈱ |
安田 正
|
執行役員 開発営業本部長 |
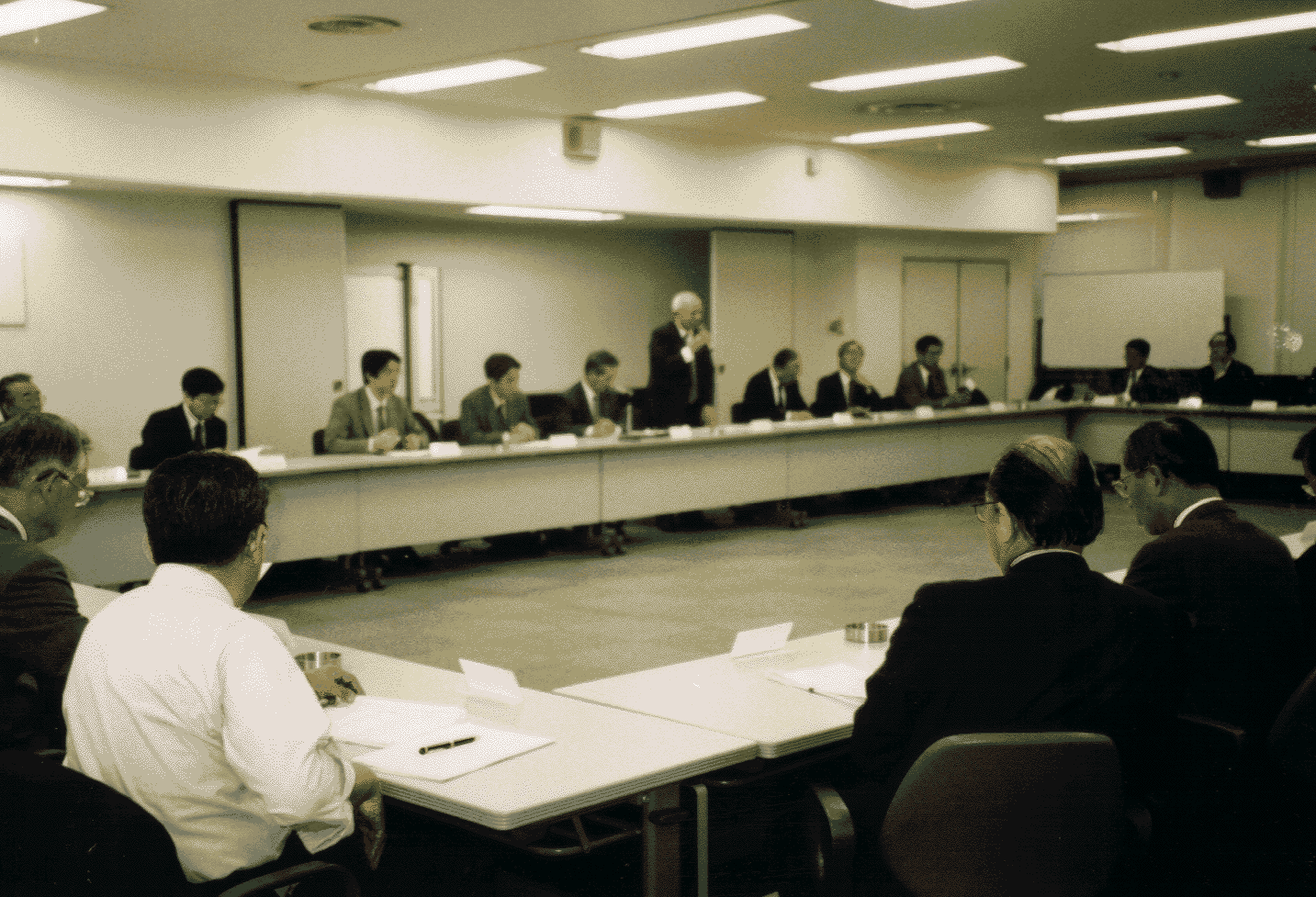 
■第20回エンジニアリング功労者賞受賞者紹介■
<グループ表彰> 国際協力
|
インドネシア・グレシック銅製錬所建設プロジェクトチーム |
代表者 :大市和司殿、小川光也殿 |
|
三菱マテリアル㈱、千代田化工建設㈱
|
メンバー:80名 |
|
インドネシア・ビリビリ多目的ダムプロジェクトチーム |
代表者 :丸井 哲郎 殿 |
|
㈱間組
|
メンバー:11名 |
<グループ表彰> エンジニアリング振興
|
13Cメタンプロジェクトチーム |
代表者 :酒井信二殿 、坂田啓一殿 |
|
東京ガス㈱、東京ガス・エンジニアリング㈱
|
メンバー:16名 |
|
八女西部クリーンセンター建設ダムプロジェクトチーム |
代表者 :藤尾弘幸殿 |
|
三井造船㈱
|
メンバー:17名 |
<グループ表彰> 環境国際貢献
|
台湾NOx改造プロジェクトチーム |
代表者 :外野雅彦殿 |
|
三菱重工業㈱
|
メンバー:6名 |
|
バイオテクノロジーによる油汚染土浄化プロジェクトチーム |
代表者 :辻 博和殿 |
|
㈱大林組
|
メンバー:9名 |
<グループ表彰> 特別テーマ「中小規模のプロジェクトを対象とした特別枠」
|
空気冷媒冷却システムAIRS(エアーズ)の開発普及 |
代表者 :宇田素久殿 |
|
プロジェクトチーム 鹿島建設㈱ |
メンバー:8名 |
|
画像IT技術開発グループ |
代表者 :神崎 正殿 |
|
大成建設㈱
|
メンバー:6名 |
<個人表彰> 国際協力
|
白石 暢明 殿 |
㈱熊谷組 海外本部副本部長兼バンコク地下鉄プロジェクトダイレクター |
|
福田 勝行 殿 |
鹿島建設㈱ インド・ダウリガンガ出張所長兼インドネシア・ウォノレジョダム出張所長 |
上記の表彰式は、11月15日に大手町サンケイプラザ3F会場にて執り行われます。

■地下利用推進部会・幹事会活動報告■
平成12年度に新たに編成された地下利用推進部会は4つの専門部会により、それぞれの活動を開始しています。
8月31日には、第2回幹事会が開催され、各専門部会の活動状況について報告がありました。
各部会とも正式に部会名称が決定され、活動の趣旨を確認するとともに、今後の具体的な活動内容について活発な意見交換が行われました。
1.地下利用事業性専門部会(通称:第1部会)
マスタープランに基づき、今後の地下空間利用を推進する上で、地下利用の理念、助成制度と規制、地下利用評価など地下利用促進策を研究する部会で、3つのWG(地下施設利用性向上検討WG、大深度地下利用基本構想検討WG、地下インフラ利用・整備構想検討WG)を組織して活動を開始しました。
2.都市地下専門部会(通称:第2部会)
都市のエネルギー自立性、広域熱供給システム・新エネルギー供給等、都市の新しいネットワークを対象範囲とし、生活、供給処理系、情報処理、運輸拠点など高齢化や情報化の変化に向けて新しい地下利用を研究する部会で、今年度の研究テーマは都市地下インフラを中心にし、都市リノベーションを考慮してエネルギーと物流に的を絞り調査します。
3.地下特性活用専門部会(通称:第3部会)
活動方針については地下センターの指針でもある「地下利用を環境保護や利便性等を優先して、地方の過疎
化防止や活性化に主眼をおき調査研究する。
さらに、活動の成果を地域性、実現条件等で整理し、自治体等に働きかけ、地方の抱える課題に配慮した地下空間利用のあり方を問題提起し、具体的な普及の方法を検討する。」を意識しつつ、初年度は地下特性を利用した地下施設の事例調査を行い、2年度の活動方針(テーマ選定)の目標を定める。
事例調査は、地下利用の構想・提案等により、実現した地下施設、実現しなかった地下施設を対象とし、地下特性、地域、深度、地盤特性等をどのように分類し、新たな視点からの調査研究が出来るかを検討する。
4.環境産業専門部会(通称:第4部会)
活動方針としては、広くは地球規模の問題から地域の問題に至るまでの幅広い分野に視点を置き、個々の問題の解決策を探ると共に、地下という新たな環境を利用した産業の創出に向けた調査研究活動を行います。活動の成果は現時点での実現性、緊急性等の観点から分類整理し、さらに実用化を目指した研究の立ち上げに資するものとします。
具体的活動は、3つのサブワーキンググループ(廃棄物の処理・処分・リサイクルSWG、地下空間の有効利用SWG、CO2問題・エネルギー備蓄・地下水循環SWG)を設置し、今年度はこれらのテーマのみにとらわれることなく、新しい地下空間利用のあり方、実現可能性、提案方法等を広い視野からの調査、自由な討議を主体に活動します。
2年度は初年度の成果あるいは方針を踏まえ、地下空間の特性を活かした環境産業の可能性、実現性のあるプロジェクト提案等の調査研究を行います。

■会員の皆様へのお知らせ■
○エンジニアリングシンポジウム2000開催のご案内
本年のシンポジウムは、変革の時代の中にあって21世紀のビジネスチャンスがどこにあるのかを示唆すべく、エンジニアリング産業関係者はもとより幅広いわが国産業人を対象に開催されますので、多くの方々の
ご参加をお待ち申し上げます。
なお、プログラムの詳細については、当協会のホームページ(http://www.enaa.or.jp)のTOPICS欄をご覧下さい。
*日 時 ;平成12年 11月 15日(水)10:00~17:30 、16日(木)9:30~19:00
*場 所 ;大手町サンケイプラザ(旧サンケイ会館)
*参加費 ;シンポジウム&交流会:15,750円 (消費税込み)
*統一テーマ;ニュー・ミレニアムを切り拓く-エンジニアリングの挑戦!
*申込・問合先;シンポジウム事務局 上原/伊藤/志村(TEL:03-3502-4441、FAX:03-3502-5500)
○第228回サロン・ド・エナ開催のご案内
11月はエンジニアリングシンポジウム2000開催のため、サロン・ド・エナは11月は無しで12月に開催と
なります。
日 時 :平成12年 12月 20日(水)17:30~(於:当協会6階CDE会議室)
講 師 :駒田 広也 氏 ((財)電力中央研究所 我孫子研究所 研究参事)
テーマ :「高レベル放射性廃棄物地層処分の現状と今後の展望」
講演要旨:
原子力発電所に係わる重要課題の一つである高レベル放射性廃棄物処分に関する法律が成立し、今秋には処分の実施主体が設立される見通しである。
2015年までに原子力発電所で発生する使用済み燃料を再処理したガラス固化体4万本を処分する総費用は約3兆円と算定され、21世紀のビッグプロジェクトである。
この高レベル廃棄物地層処分に関する現状ならびに国内外の動きを紹介するともに、今後の処分地選定、処分地調査、施設設計、安全評価、施設建設、廃棄体埋設、処分場閉鎖等の一連の処分事業の計画を報告する。
さらに、技術的課題を提示し、今後を展望する。
申込要領:FAXで事務局へお申し込み下さい。申込多数の場合は先着順で締め切らせていただきます。
地下開発利用研究センター 事務局 中村
(TEL:03-3502-3671/FAX:03-3502-3265)

■新聞記事からの紹介■
○「原子力発電環境整備機構」が発足-電事連-
(2000.10.19日付 日刊工業新聞より)
電気事業連合会は18日、高レベル放射性廃棄物処分の実施主体となる「原子力発電環境整備機構」(東京都港区芝4の1の23、外門一直理事長、03・4513・1111)が同日、通産相から設立認可を受け発足したと発表した。
同機構の運営・処分地建設費は電力会社の拠出金で賄う。当面、来年3月末までは約10億円の借入金で運営する。
高レベル廃棄物の処分費用総額は2兆9305億円。
ガラス固化体1本当たりの処分費用は約3509万円、1㌔㍗時当たり処分費用は約13銭。
政府は9月末の閣議で、使用済み燃料の再処理後に発生する高レベル廃棄物(ガラス固化体)の量を、2013年ごろには総数で約3万本、2020年ごろには約4万本に達する-との予測を承認した。
外門理事長は「地層の文献調査などからスタートし、社会全体の理解を得るための基礎固めに取り組む」としている。

|