|

第150号/2002.3
■「高効率熱電変換素子開発先導研究」の活動総括と今後の展望
■第4回国際ガスハイドレート会議開催案内
■PM資格認定制度発足の紹介
■会員の皆様へのお知らせ
■新聞記事からの紹介
■「高効率熱電変換素子開発先導研究」の活動総括と今後の展望■
当センターでは表記先導研究の内、材料、素子製造、システムに関する研究を(財)省エネルギーセンターより再委託を受け、平成12、13年度の2年間にわたり研究を行い、このたびほぼ終了しましたのでご報告いたします。また経済産業省では先導研究の結果を受けて、来年度より総合研究開発プロジェクトを立ち上げることを決定しましたのであわせてご報告いたします。
1.先導研究の目的
熱電発電技術は、現状技術では利用困難な産業・民生・運輸部門から発生する未利用熱エネルギーの有効利用方法として、半導体を利用して未利用熱エネルギーを電気エネルギーに変換し発電を行うものです。このためには材料、素子、システムの開発が必要ですが、先導研究では本格的な研究開発を立ち上げる前に、技術的ブレークスルーや実用化した場合の経済性の見通し、国レベルでの環境負荷削減効果等について調査研究を行いました。
2.研究成果の概要
(1)材料(革新的材料の探索)
従来熱電発電が普及しなかった原因の一つに半導体の熱電変換効率の低さが挙げられます。これをブレークスルーするため、高効率化の可能性を秘めた実用化に近い熱電変換材料を7種類に絞込み、研究を行い、実用化の見通しを得ました。
(2)素子製造
一般に素子は大きな熱応力を受けるため、長時間安定した運転ができるためには熱応力の緩和や、劣化対策が不可欠です。これに関する様々な対策を調査研究し、一部の材料については試作を行い良好な結果を得ました。
(3)システム
熱電発電の適用分野として、産業、民生、自動車が考えられますが、当協会は産業・民生分野を担当しました(自動車は省エネセンター殿担当)。
産業用として製鉄所、清掃工場、電気抵抗炉への適用、民生用としてコジェネ、給湯器、パソコンへの適用を取上げ、概念設計、経済性試算、環境負荷削減効果の試算を行ない、実用化への見通しを得ました。
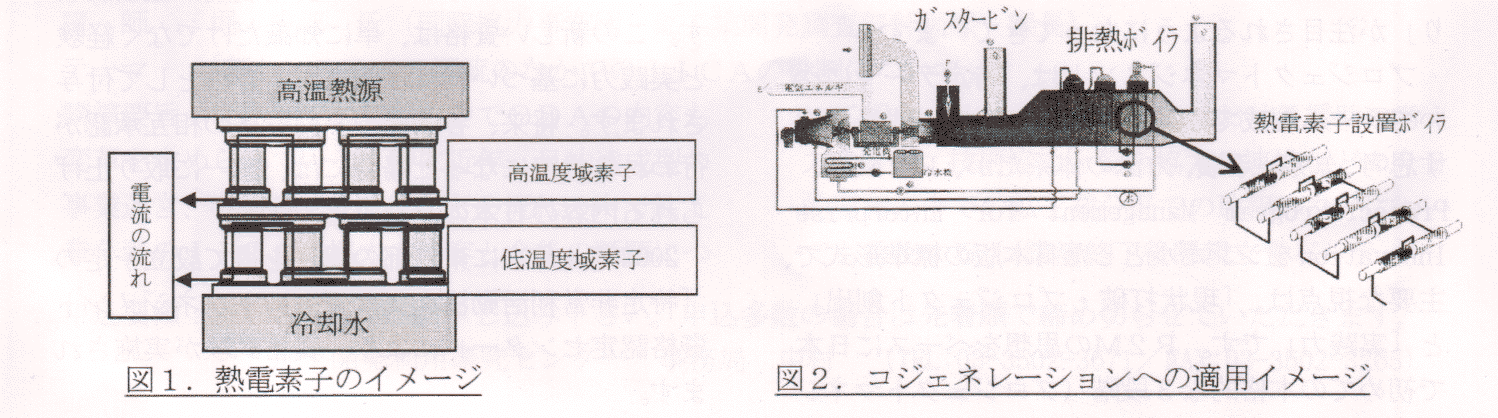
3.今後の展開
経済産業省では、2010年におけるCO2削減目標を達成するために様々な施策を講じていますが、研究開発面からこれを達成すべく『革新的地球温暖化対策技術プログラム』を設定しています。熱電発電に関しては、先導研究の成果を受けて、本プログラムの中のプロジェクトのひとつとして、来年度から五年間の予定で総合研究開発プロジェクトを開始することを決定いたしました。
総合研究開発プロジェクト概要:
(1)プロジェクト名:高効率熱電変換システムの開発
(2)施策・事業の概要:産業・民生部門において発生する熱エネルギーの多くは、未利用のまま排熱エネルギーとして排出されている。熱電変換素子開発および熱電変換システムを開発することで、これら未利用エネルギーを電気エネルギーとして利用し、省エネルギーおよび地球温暖化ガス
排出削減に資する。
(3)プロジェクト実施期間:平成14年度より5年間
(4)事業:補助事業(国の補助率2/3)
(5)今後の予定:
・3月:経済産業省補助金交付先公募開始
・5月:公募〆切り
・7月:補助金交付先決定、研究開始
このように熱電変換素子およびシステム技術は地球温暖化ガス排出抑制型社会の構築に大きく貢献することが期待され、国も積極的に支援してゆくことが決まりました。また当センターにとっては2年間にわたって行なってきた先導研究が本格的研究開発プロジェクトとして実を結んだ結果となりました。この間ご協力頂いた会員企業の方々に深く感謝いたします。今後当センターでは先導研究の研究実績を生かすべく、本プロジェクトに積極的に参加してゆく所存ですので、紙上を借りて、会員企業各位の更なるご支援をお願いする次第です。(技術開発第2部 大木記)

■第4回国際ガスハイドレート会議開催案内■
当センターで「天然ガス固体化地下貯蔵システムに関する調査研究」の委員長をお願いしている森 康彦慶応義塾大学理工学部機械工学科教授が主催される「第4回国際ガスハイドレート会議」が、2002年5/19(日)~5/23(木)、横浜シンポジア(横浜市中区山下町)で開催されます。
論文の内容としては、天然ガスハイドレート(メタンハイドレート)の探査・掘削・生産試験、天然ガスハイドレート層の成因、ガスハイドレート生成系の熱力学、ガスハイドレートの諸物性、ガスハイドレートの生成・分解の動力学、ガスパイプラインの閉塞防止技術、地球温暖化問題とガスハイドレート、分離・濃縮技術へのガスハイドレートの利用、ガスハイドレートを蓄冷媒体とする夜間電力蓄冷、ガスハイドレートによる天然ガスの貯蔵・輸送等が見込まれています。
(詳細につきましては、ホームページ(http//hydrate.welcome.to/)をごらんください)

■PM資格認定制度発足の紹介■
日本企業は、「ものづくり」中心の発想から「仕組みづくり」による再生に転換しつつあり、そこでプロジェクトマネジメントによる「仕組みづくり」が注目されるようになってきています。
プロジェクトマネジメントは、特定テーマについてチーム編成で期限を区切って着実に成果を出す思考、知恵、手順、方法の体系だが、P2Mは、Project&Program
Management for Enterprise Innovationをシンボルとした日本版の標準形式で、主要な視点は、「現状打破・プロジェクト創出」と「実践力」です。P2Mの思想をベースに日本で初めての本格的な3段階(プロジェクトマネジメント・スペシャリスト、プロジェクトマネジャー、プロジェクトマネジメント・アーキテクト)のプロジェクトマネジメント資格制度が生まれます。この新しい資格は、単に知識だけでなく経験と実践力に基づいた真に価値ある資格として付与されます。将来、各国間のPM資格の相互承認が行われる状況になった場合には、第一に取り上げられる内容の日本のPM資格です。
2002年4月末に東京都の認証を得て設立予定の「特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター」により、資格試験が実施されます。
○PM資格認定制度説明会開催案内
PM資格認定制度の概要とセンターの事業内容等についての説明会が下記により開催されます。
*日 時 :平成14年3月8日(金)13:00~16:00
*場 所 :全電通ホール(御茶ノ水)
*参加 費:無料
*申込方法:期日が迫っていますが、参加ご希望の方は、「http//www.enaa.or.jp/PMCC/index.htm」にアクセスし、「参加申込書」に必要事項をご記入の上、Eメールにてお申し込み下さい。(満員の節はご容赦ください)

■会員の皆様へのお知らせ■
○平成13年度日帰り見学会のご案内(申込お急ぎください!!)
さいたま新都心における地下関連施設と春日部市郊外の首都圏外郭放水路現場をまわります。
・期 日:平成14年3月14日(木) 8:50~18:00
・見学先:東京電力「さいたま新都心電力供給施設」、埼玉県道路管理課「さいたま新都心共同溝」、首都
高速道路公団「高速大宮線・新都心地区トンネル工事」、国土交通省関東地方整備局「首都圏外
郭放水路」
・参加費:5000円(定員30名)
・申込期限:3月7日(木)(期限が過ぎていても、参加の可能性がありますので問合せください)
・申込・問合せ先:地下センター高見、中村(TEL:03-3502-3671/FAX:03-3502-3265)
見学先の概要:
①東京電力(株)「さいたま新都心電力供給施設」(埼玉県さいたま市)
始めに北与野の変電所の一連の施設を見学します。上尾から地下トンネルで送電されてきた高圧電力を受けて屋内の変電所で66KVに変圧して市街地地下の洞道を経由して新都心へと導いています。
②埼玉県道路管理課「さいたま新都心共同溝」(埼玉県さいたま市)
上下水道、中水道、通信、電力、ガス、熱供給、CATV等の共同溝が土地造成と併せて整備され、災害に強い町になりました。
③首都高速道路公団「高速大宮線・新都心地区トンネル工事」(埼玉県さいたま市)
新都心基盤整備の一環として都心とを結ぶ高速大宮線が建設中です。新都心地区は地下トンネルで立体通過します。早期開通が待たれる地下トンネルと新都心ランプを見学します。
④国土交通省関東地方整備局「首都圏外郭放水路」(埼玉県春日部市)
慢性的な浸水地帯である埼玉県北東部の平坦な中川流域低地において、浸水被害解消を目的に大落古利根川~中川~江戸川を地下約50mでつなぎ、巨大なガスタービン4基で放水するビッグプロジェクトが施工中ですが、今回は掘進中の第4工区を見学します。
○第242回サロン・ド・エナ開催のご案内
日 時 :平成14年3月20日(水)17:30~(於:当協会6階CDE会議室)
講 師 :堀 史郎 氏(国際協力事業団 鉱工業開発調査部計画課 課長)
テーマ :「新しいODAの潮流のなかでのJICAの役割について」
講演要旨:世界経済の激動の中でODAの内容も変革を求められている。特に近年、目的達成型の事業運営、事業のソフト化などの流れの中で鉱工業分野のJICAの協力の内容と今後の話題について紹介する。又、技術協力における援助の考え方の変化、技術協力と資金協力の連携などの今日的要請の中での鉱工業分野での取組みなどについても言及する。(講演終了後懇親立食パーティ)
申込要領:mailまたはFAXで下記1から4を事務局へご連絡下さい。
1.会社名 2.氏名 3.所属・役職 4.連絡先
地下開発利用研究センター 事務局 中村
(TEL:03-3502-3671/FAX:03-3502-3265)
mailto:gec-adm@enaa.or.jp
申込多数の場合は先着順で締め切らせていただきます。
申し込み受付のできない場合のみご連絡いたします。
○平成14年度エンジニアリング功労者表彰候補の推薦について
当協会では昭和56年度より「エンジニアリング功労者表彰制度」を設け、エンジニアリング産業の振興発展に貢献し、その功績が特に顕著であると認められる方々に対し表彰を行っており、本年度は22回目となります。本年度のこの賞に相応しい候補について、現在、会員各社あて推薦書の提出をお願いいたしておりますので、本賞に相応しいグループまたは個人についてご推薦いただきたく、ご案内いたします。
平成14年度は、「国際協力」「エンジニアリング振興」「環境貢献」および「特別テーマ」について候補の募集を行います。本年度はプロジェクトマネジメントに注目し、その効果的な活用・向上により優れた成果を上げたか否かを重点に審査されます。また、本年度の特別テーマは昨年度同様「中小規模のプロジェクトを対象とした特別枠」としますが、特に新規分野の開拓、需要創出に貢献したもの、中堅・中小エンジニアリング業の振興に寄与するもの等について評価いたします。
なお、個人表彰についても、国際協力または、エンジニアリング振興において、その功績が特に顕著である方々を積極的にご推薦願います。
受賞者の選考:エンジニアリング功労者選考委員会委員長 石井威望氏(東京大学名誉教授)によって行われます。
表彰の時期:平成14年7月中旬頃表彰式が執り行われる予定です。
募集締切日:平成14年3月29日
問い合わせ先: 業務部 船越・小倉(TEL:3502-4441、FAX:3502-5500)

■新聞記事からの紹介■
○モンゴルの空に風車
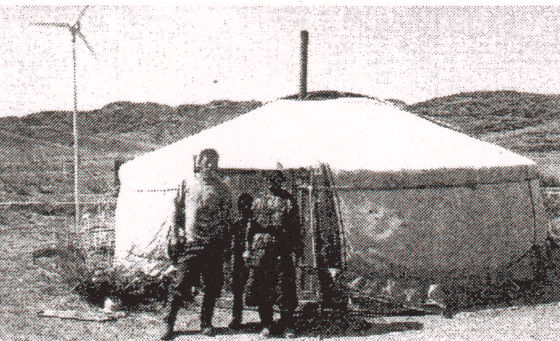 宮崎県の国立都城工業高等専門学校の教師グループが、モンゴル国の遊牧民のために、風力発電による「灯りを贈る」という活動を進めていた。これに協賛した電気メーカーが、モンゴルの「ハルブフ・ツガーン遺跡を守る会」へ弱風型風力発電機1基と支援金を寄贈した。 宮崎県の国立都城工業高等専門学校の教師グループが、モンゴル国の遊牧民のために、風力発電による「灯りを贈る」という活動を進めていた。これに協賛した電気メーカーが、モンゴルの「ハルブフ・ツガーン遺跡を守る会」へ弱風型風力発電機1基と支援金を寄贈した。
寄贈された発電機は、風速1m/秒という弱風から発電できるもので、モンゴルと日本の友好関係を築く一助になることが期待されている。
(編集者記)これこそ「ものつくり」の真髄で、技術革新が、世界の恵まれない人に文明の利器(固有の文明に悪影響を与えない)の恩恵を与えることができるわけで、日本の技術者が進むべき道を示してくれた新聞記事だなと感じた。モンゴルに無数の風力発電機が林立する日も近いのではとの思いを抱かせた。
舌句雑感:もしも世界の人口が100人だったなら・・・・。20人が世界の90%の富を握ります。食糧援助よりも化粧品に40倍のお金が使われるあいだに、15人は飢えで苦しみます。そして教育よりも武器に10倍多くお金が使われているため、16人は字を読むことができません。20人は、家に1台以上のテレビを持っていますが、17人には家すらありません。この20人は彼らの持つ富のたった0.2%で貧困を終わらせることのできる最初の世代です。そしていま、家でテレビを見ているあなたは、その1人かもしれません。(オランダで放映された国連開発計画のTV-CM、「広告批評」誌2001年11月号より)
"100人の村"で検索すると、いろんなホームページがでてくるが、一例としては、(http://urawa.cool.ne.jp/tanaka3/peace.html)がある。一度覗かれてみることをお勧めする。
現実を見ているととてもそうとは思えないが、奇妙なことだが、世界の預言者の宣託によると、この混迷の世界を救う救世主は日本から出るということで一致している。このメールのリレーは、アメリカから始まったが、大きな果実にするのはわれわれかもしれない。 (GECニュース編集者) |

|

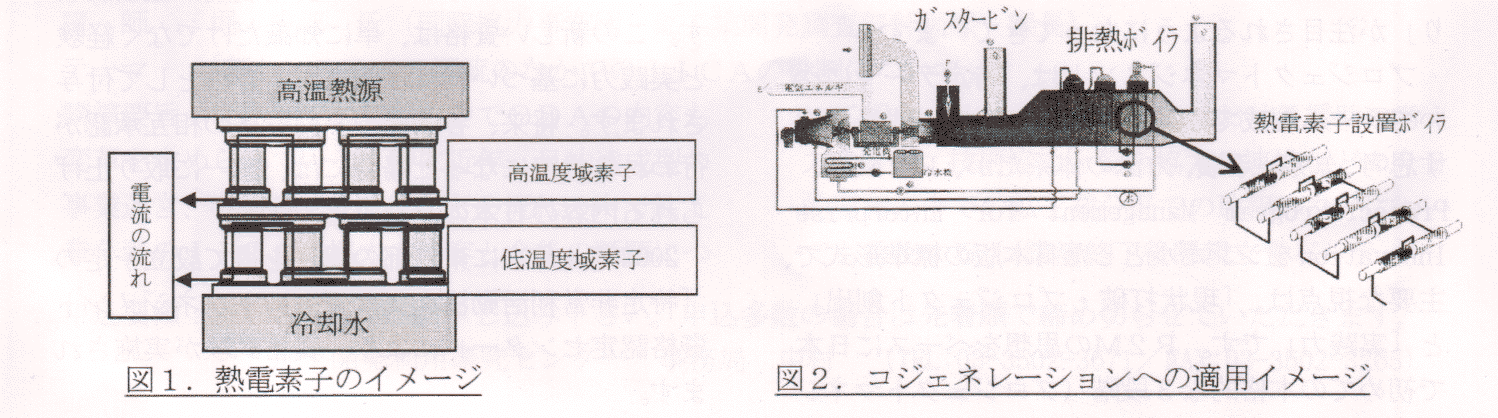
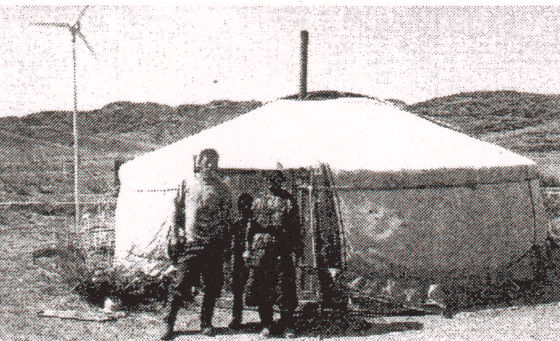 宮崎県の国立都城工業高等専門学校の教師グループが、モンゴル国の遊牧民のために、風力発電による「灯りを贈る」という活動を進めていた。これに協賛した電気メーカーが、モンゴルの「ハルブフ・ツガーン遺跡を守る会」へ弱風型風力発電機1基と支援金を寄贈した。
宮崎県の国立都城工業高等専門学校の教師グループが、モンゴル国の遊牧民のために、風力発電による「灯りを贈る」という活動を進めていた。これに協賛した電気メーカーが、モンゴルの「ハルブフ・ツガーン遺跡を守る会」へ弱風型風力発電機1基と支援金を寄贈した。