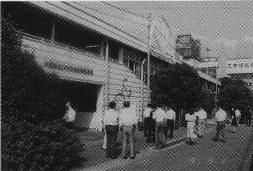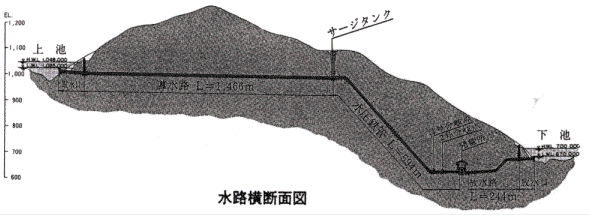戞俀俆崋乛侾俋俋侾丏俋 仭暯惉俁擭搙搒巗晹偵偍偗傞岠棪揑抧壓挀幵応僔僗僥儉偵娭偡傞挷嵏尋媶暘壢夛
仭戝宆僾儘僕僃僋僩尰嫷仭
暯惉俁擭搙戝僾儘丒乽戝怺搙抧壓嬻娫奐敪媄弍乿偺尋媶奐敪偵偮偄偰偼丄嶐擭搙偵堷偒懕偒丄怴僄僱儖僊乕丒嶻嬈媄弍憤崌奐敪婡峔乮俶俤俢俷乯偲偺娫偵埾戸宊栺傪掲寢偟丄塻堄尋媶奐敪傪恑傔偰偄傞偲偙傠偱偁傞偑丄杮擭搙偼摿偵梫慺媄弍幚尡傪庡懱偲偟偰丄婎杮愝寁傪庢傝傑偲傔傞偙偲偵側傞偑丄杮擭搙忋婜偺廔椆傕娫嬤偲側傞偺偱拞娫曬崘偺庢傝傑偲傔偵拝庤偡傞帪婜偵棃偰偄傞丅
仭暃乆搒怱拞怱奨嵞惗寁夋尋媶夛敪懌仭
俋寧俇擔丄暃乆搒怱拞怱奨嵞惗寁夋尋媶夛乮尋媶夛挿丄朄惌戝妛嫵庼丂搉晹梌巐榊巵乯偺戞侾夞埾堳夛偑奐嵜偝傟偨丅杮尋媶偼抧壓僙儞僞乕敪懌屻偼偠傔偰幚巤偡傞僾儘僕僃僋僩悇恑帠嬈偺侾僥乕儅偱偁傞丅尋媶撪梕偼暘壢夛僥乕儅乽抧壓嬻娫傪妶梡偟偨抧嬫嵞奐敪僔僗僥儉乿傪堷宲偓丄搶嫗嬤峹偺暃乆搒怱偺侾偮傪僒儞僾儕儞僌偟丄偦偺墂慜抧嬫傪懳徾偲偟偰丄僯儏乕僼儘儞僥傿傾偲偟偰偺抧壓嬻娫妶梡偺庤朄摍傪摫擖偟丄嬶懱揑側嵞奐敪帠嬈寁夋偵偮偄偰偺採埬傪峴偆偙偲傪栚揑偲偡傞丅傑偨丄廬棃偺僴乕僪巜岦偺奨偯偔傝僔僗僥儉偵戙傢傞怴偨側僜僼僩巜岦僔僗僥儉傕尋媶偡傞丅棃擭偺係寧傑偱尋媶妶摦傪峴偄惉壥傪偲傝傑偲傔傞梊掕偱偁傞丅
仭暯惉俁擭搙搒巗晹偵偍偗傞岠棪揑抧壓挀幵応僔僗僥儉偵娭偡傞挷嵏尋媶暘壢夛仭
杮暘壢夛偼暯惉俀擭搙傪弶擭搙偲偡傞俀儢擭偺宲懕尋媶偱偁傝丄暯惉俀擭搙偺尋媶惉壥偵偮偄偰偼俧俤俠僯儏乕僗俉寧崋偵婰嵹偝傟偰偄傞捠傝偱偁傞丅 杮擭搙偼拞栰嬫偺嫤椡傪摼偰丄拞栰墂杒岥峀応傪嬶懱揑側働乕僗僗僞僨傿偺懳徾偲偟偰庢傝忋偘傞偙偲偵側傝丄怴埾堳偲偟偰搶嫗搒偺屆愳壽挿丄拞栰嬫偺愇恄壽挿丄嶳娸壽挿丄搶戝偺拞懞彆庤偍傛傃擔棫憿慏乮姅乯偺奺埾堳偵嶲壛偟偰偄偨偩偒丄俀擭搙偵憹偟偰尋媶懱惂傪廩幚偝偣偰敪懌偟偨丅俉寧俇擔偵戞侾夞暘壢夛傪奐嵜偟丄俋寧俀擔偵偼拞栰墂廃曈偺尰抧挷嵏傪娷傔偨戞侾夞嶌嬈晹夛傪奐嵜偟偨丅 杮擭搙偼棫抧忦審偵懳墳偟偨嵟揔側抧壓挀幵応僔僗僥儉傪専摙偡傞丅偝傜偵働乕僗僗僞僨傿傪捠偟偰専摙偟偨抧壓挀幵応僔僗僥儉偵偮偄偰専徹偟丄偦偺幚尰偺曽嶔傪採尵偡傞丅
俀丏尋媶撪梕
俁丏尋媶懱惂
丂 暯惉俁擭搙搒巗晹偵偍偗傞岠棪揑抧壓挀幵応僔僗僥儉偵娭偡傞挷嵏尋媶暘壢夛柤曤
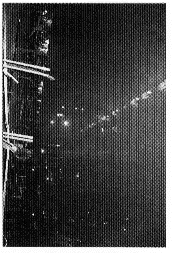
儅僗僞乕僾儔儞愱栧埾堳夛偺抧斦挷嵏媄弍晹夛偱偼丄晹夛偺儊儞僶乕偵傕嶲壛捀偄偰偄傞搶嫗揹椡噴揳偺偛岲堄偵傛傝丄幹旜愳梘悈敪揹強偺寶愝忬嫷偺尒妛傪幚巤偟丄婱廳側尋媶妶摦偲偡傞偙偲偑偱偒偨丅埲壓偦偺奣梫傪曬崘偡傞丅 斢壞偲偄偆傛傝偼丄廐娫嬤偺椓晽偲彫塉偺拞丄撨恵墫尨偵廤崌偟偨堦峴俀俆柤乮寚惾俁柤乯偼丄傑偢憤寶愝強偱慡懱愢柧傪庴偗丄抧壓敪揹強丄壓僟儉丄忋僟儉偺弴偱尒妛傪偝偣偰偄偨偩偄偨丅搶嫗揹椡幹旜愳梘悈敪揹強偼丄徍榓俇侾擭侾侽寧忋僟儉岺帠傪拝岺偟偰埲棃丄暯惉俇擭俈寧偺侾崋婡乮俁侽枩倠倂乯丄暯惉俈擭俈寧偺俀丒俁崋婡乮俁侽枩倠倂亊俀乯偺塣揮奐巒傪栚巜偟丄尰嵼慡懱恑捇棪俇俀亾乮撪搚栘俇俉亾乯偲偺偙偲偱尰応慡懱偑妶婥偵枮偪偰偄偨丅 抧壓敪揹強偼崅偝俆侾丏係倣暆俀俋丏侽倣挿偝侾俇俆丏侽倣偺嫄戝嬻摯偑姰惉偟丄捈棫偡傞懁暻丄偦偺懁暻偵懪偨傟偨戲嶳偺傾儞僇乕丄栺侾俈侽侽屄偵傕媦傃寁婍偵傛傞娤應僔僗僥儉摍丄乬憂憿乭偺姶摦偑傂偟傂偟偲偣傑偭偰棃傞傕偺偱偁偭偨丅 壓僟儉乮僐儞僋儕乕僩廳椡僟儉丄俫亖侾侽係倣丄倁亖侾侽俆侽枩倣3乯偱俼俠俢岺朄偵傛傞掔懱偺僐儞僋儕乕僩懪愝岺帠傪尒妛偺屻丄忋僟儉乮昞柺偟傖悈宆儘僢僋僼傿儖僟儉丄俫亖俋侽丏俆倣丄倁亖侾侾俋侽枩倣俁乯偺偟傖悈傾僗僼傽儖僩懪愝忬嫷傪尒妛偟偨丅忋僟儉偼惙棫偰偑姰椆偟丄尰嵼俁憌栚偺傾僗僼傽儖僩僼僃乕僔儞僌拞偱丄栺俁侽丆侽侽侽倣3偺幗崟偺柺偺強乆偐傜棫偪搊傞搾婥偲丄嶳柖偑晽偵棳傟偰偄傞條巕偼惓偵埑姫偱偁偭偨丅慡懱偵婽楐偺懡偄娾斦偱搚栘岺帠偵偼懡偔偺嬯楯偲岺晇偑敽偭偨偙偲偲悇掕偝傟偨丅偛愢柧偲偛埬撪傪偟偰捀偄偨抾壓媄弍壽挿偵怺偔姶幱偟偰尒妛夛傪廔椆偟偨丅偦偺傑傑撨恵崅尨拞暊偺廻幧偵擖傝丄梉怘屻倂俧侾丄倂俧俀偵暘偐傟偰儈乕僥傿儞僌傪幚巤偟傑偟偨偑丄嵟屻偼丄傎傏慡堳偑堦幒偵廤傑偭偰丄尋媶妶摦偺斀徣傗傜丄崅彯乮丠乯側媄弍択媊偑怺峏偵傑偱偍傛傃傑偟偨丅 梻擔屵慜拞偺倂俧媦傃慡懱晹夛偱尋媶曬崘彂偺尨峞傪傎傏俋侽亾姰椆偝偣丄摉晹夛偺栺敿擭偵傢偨傞尋媶妶摦偺幚幙揑妶摦傪摟偒偲偍偭偨崅尨偺嬻婥偺拞偱桳堄偵廔椆偝偣傑偟偨丅 乮噴僟僀儎僐儞僒儖僞儞僩丂丂揷懞婰乯
仜媏娫抧壓愇桘旛拁婎抧丄娾斦抧壓僞儞僋偺孈嶍姰椆乮擔姧寶愝岺嬈怴暦丂俉寧俀侽擔乯 媏娫抧壓愇桘旛拁婎抧乮垽昋導墇抭孲媏娫挰乯偺娾斦抧壓僞儞僋偺孈嶍岺帠偑姰椆丄抧壓偵弌尰偟偨嫄戝側抧壓嬻娫傪棙梡偟偰丄偙偺傎偳儊儌儕傾儖僀儀儞僩偑奐偐傟偨丅乽愇桘偺挋憼偑巒傑偭偨傜擇搙偲拞偵偼擖傟側偄丅岺帠偵偛棟夝偲偛嫤椡傪偄偨偩偄偨廃曈抧尦廧柉偺曽乆偵姶幱偺婥帩偪傪崬傔偰壗偐婰擮峴帠傪峴偄偨偐偭偨乿偲偄偆俆幮俰倁偺敪埬偵傛傞嵜偟丅乽僼傽儞僞僕傾丒壒偲岝偺儁乕僕僃儞僩乿偲戣偟丄娾斦抧壓僞儞僋偺拞偱岺帠婰榐價僨僆偺塮幨傗儗乕僓乕岝慄傪巊偭偨儔僀僥傿儞僌僔儑乕丄僔儞僙僒僀僓乕墘憈側偳偑孞傝峀偘傜傟偨丅抧尦廧柉丄岺帠娭學幰傜俉侽侽恖偑嶲壛丄摿偵壞媥傒拞偺巕嫙偨偪偼丄抧壓嬻摯偱偺尪憐揑側墘弌偲戝宆寶婡傪栚偺摉偨傝偵偟栚傪婸偐偣偰偄偨丅
仜俵俵俀侾偵係俆侽侽僩儞偺抧壓挋悈憛乮擔杮宱嵪怴暦俉寧俀俁擔乯
仜怴嫶墂惣岥傪婎慴挷嵏丄抧壓僱僢僩儚乕僋傪宍惉乮擔姧寶愝岺嬈怴暦丂俉寧俀俁擔乯
仜壓悈摴帠嬈抍梊嶼梫媮侾俉亾憹偺俁侽係係壄墌廔枛張棟応寶愝係侾侽僇強偵乮擔姧岺嬈怴暦丂俉寧俀俉擔乯
仜怴僄僱儖僊乕嵿抍丂埑弅嬻婥挋憼僈僗僞乕價儞帋尡僾儔儞僩帠柋強傪奐愝
仜搶嫗搒丄搚栘尋媶僙儞僞乕偲柉娫侾俉幮偱峔惉偡傞帺桼抐柺僔乕儖僪岺朄尋媶夛偼廲炆墌僔乕儖僪偺幚徹幚尡廔椆丅棃弔丄崙嵺夛媍偱敪昞乮擔姧寶愝岺嬈怴暦丂俉寧俁侽擔乯
仜僗僞乕儕儞僌巵棃朘 暷崙壢妛嵿抍偺尋媶僾儘僕僃僋僩乽擔暷偵偍偗傞抧壓寶愝媄弍乿偺堦彆偲偡傞偨傔朘擔拞偺儈僱僜僞戝妛彆嫵庼僗僞乕儕儞僌巵偑俉寧俀俋擔摉僙儞僞乕傪朘栤偝傟偨丅摨巵偼栺侾侽擔娫擔杮偵懾嵼偝傟偦偺娫戝庤寶愝夛幮丄彅姱挕丄尋媶婡娭傪朘栤偝傟偰偄傞丅摉僙儞僞乕偱偼僙儞僞乕偺奣梫丒挷嵏尋媶妶摦偵偮偄偰愢柧偟丄堄尒岎姺傪峴偭偨丅傑偨摨巵偑嫽枴傪傕偨傟偨曬崘彂傪悢晹嵎偟忋偘傞偙偲偲側偭偨丅 仜僒儘儞丒僪丒僄僫乮戞侾俀俋夞乯奐嵜埬撪
仜怴婯擖夛亙俉寧俆擔亜 仜僄儞僕僯傾儕儞僌僔儞億僕僂儉乫俋侾奐嵜埬撪
|