
戞俉俉崋乛侾俋俋俈丏侾
仭擭摢強姶
仭儈僯僪乕儉娐嫬杊嵭憤崌幚尡
仭夛堳偺奆條傊偺偍抦傜偣
仭暯惉俉擭搙崙撪尒妛夛曬崘
仭戞侾俉俈夞僒儘儞丒僪丒僄僫奐嵜偍抦傜偣
仭擭摢強姶仭
捠彜嶻嬈徣娐嫬棫抧嬊嶻嬈巤愝壽挿丂姡丂晀堦巵
 暯惉俋擭偺怴弔傪寎偊傞偵摉偨傝丄嬣傫偱偛垾嶢傪怽偟忋偘傑偡偲偲傕偵丄堦尵強姶傪弎傋偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅奆條屼崅彸偺偲偍傝丄嵟嬤偺変偑崙宱嵪偼丄娚傗偐側夞暅孹岦偑懕偄偰偼偄傞傕偺偺丄屬梡傪拞怱偵側偍尩偟偄忬嫷偑懕偄偰偄傑偡丅摿偵丄撪奜宱嵪娐嫬偺寖曄偵傛傞嶻嬈嬻摯壔偵懳偡傞寽擮摍偑堷偒懕偒崅傑偭偰偍傝丄尰忬偺儁乕僗偱嶻嬈嬻摯壔偑恑峴偡傟偽丄惢憿嬈慡懱偺屬梡偼丄崱屻俆擭娫偱侾俀係枩恖掱搙尭彮偡傞偲偄偆捠彜嶻嬈徣偺帋嶼寢壥傕弌偰偄傑偡丅
暯惉俋擭偺怴弔傪寎偊傞偵摉偨傝丄嬣傫偱偛垾嶢傪怽偟忋偘傑偡偲偲傕偵丄堦尵強姶傪弎傋偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅奆條屼崅彸偺偲偍傝丄嵟嬤偺変偑崙宱嵪偼丄娚傗偐側夞暅孹岦偑懕偄偰偼偄傞傕偺偺丄屬梡傪拞怱偵側偍尩偟偄忬嫷偑懕偄偰偄傑偡丅摿偵丄撪奜宱嵪娐嫬偺寖曄偵傛傞嶻嬈嬻摯壔偵懳偡傞寽擮摍偑堷偒懕偒崅傑偭偰偍傝丄尰忬偺儁乕僗偱嶻嬈嬻摯壔偑恑峴偡傟偽丄惢憿嬈慡懱偺屬梡偼丄崱屻俆擭娫偱侾俀係枩恖掱搙尭彮偡傞偲偄偆捠彜嶻嬈徣偺帋嶼寢壥傕弌偰偄傑偡丅
偙偺傛偆側忬嫷偺拞偱丄崙柉惗妶偺朙偐偝傪幚姶偱偒傞幮夛傪幚尰偡傞偨傔偺怴偨側嶻嬈妶摦偲偟偰丄傑偨怴婯嶻嬈暘栰偺憂弌傪峴偆偨傔偵傕抧壓棙梡偺懀恑偑戝偒側惌嶔壽戣偲側偭偰偄傑偡丅偙偺偨傔丄嶐擭侾俀寧侾俈擔偵妕媍寛掕偝傟偨乽宱嵪峔憿偺曄妚偲憂憿偺偨傔偺僾儘僌儔儉乿偵偍偄偰傕丄崱屻惉挿偑婜懸偝傟傞侾俆暘栰偺偆偪乽搒巗娐嫬惍旛娭楢暘栰乿偵偰崱屻丄戝怺搙抧壓嬻娫奐敪媄弍偺奐敪偺昁梫惈偑帵偝傟偰偄傑偡丅
偦偆偟偨拞丄抧壓嬻娫棙梡偵拞怱揑側栶妱傪壥偨偟偰偙傜傟傑偟偨抧壓奐敪棙梡尋媶僙儞僞乕偵偍偐傟傑偟偰偼丄怴偨側媄弍奐敪偲偟偰戝怺搙抧壓嬻娫奐敪媄弍乮崅惛搙抧壓峔憿昡壙丄抧壓嬻娫峔抸丄抧壓娐嫬丒杊嵭摍偺媄弍妋棫乯偺奐敪傪峴偭偰偒偰偍傝丄塃帠嬈偼惤偵堄媊怺偄傕偺偱偁傝傑偡丅
崱屻丄戝怺搙抧壓偺棙梡偲偟偰偼丄揝摴丄抧壓暔棳僔僗僥儉丄僄僱儖僊乕挋憼丄抧壓惔憒岺応丄僈僗娗摍側偳偑峫偊傜傟傑偡偑丄偦偺棙梡偵摉偨偭偰偼戝怺搙抧壓偵偍偗傞搚抧強桳尃丄曗彏摍偺昁梫惈偺桳柍偵偮偄偰夝寛偟側偗傟偽側傜側偄廳梫側栤戣偑懡偔巆偝傟偰偄傑偡丅惌晎偲偄偨偟傑偟偰傕椪帪戝怺搙抧壓棙梡挷嵏夛傪愝抲偟丄暯惉俈擭侾侾寧偵弶夛崌偑奐嵜偝傟偰埲棃丄媄弍丒埨慡丒娐嫬晹夛丄朄惂晹夛傪怴偨偵愝抲偟丄戝怺搙抧壓偺揔惓丄寁夋揑側棙梡偺妋曐偲岞嫟揑棙梡偺挷嵏丒怰媍偑峴傢傟偰偄傑偡丅暯惉俉擭搙枛偵偼拞娫曬崘偑傑偲傔傜傟丄暯惉侾侽擭偺弔崰傪栚搑偵嵟廔摎怽偑弌偝傟傞梊掕偵側偭偰偍傝傑偡丅捠彜嶻嬈徣偲偟偰傕偙偺専摙壽戣偵愊嬌揑偵娭梌偟偰偄偔偲偲傕偵丄抧壓奐敪棙梡尋媶僙儞僞乕偑偙傟傑偱偵拁愊偟偰偒偨尋媶惉壥偑朙偐偝偲妶椡偺偁傞宱嵪幮夛偺峔抸偵戝偄偵栶棫偮傕偺偲婜懸偟偰偄傞偲偙傠偱偁傝丄崱屻偲傕抧壓奐敪棙梡尋媶僙儞僞乕偺帠嬈偵偱偒傞尷傝偺巟墖傪峴偭偰偄偔強懚偱偁傝傑偡丅
抧壓嬻娫偺棙梡懀恑偼丄嬻娫僗儁乕僗偑尷傜傟偨変偑崙丄偲傝傢偗戝搒巗偵偍偄偰怴偨側宱嵪丒幮夛妶摦偺応傪奼偘傞偆偊偱丄傑偨怴婯嶻嬈傪憂弌偡傞偆偊偱戝曄桳朷側暘栰偱偁傝丄俀侾悽婭偵岦偗偰偺僼儘儞僥傿傾偲埵抲偯偗傜傟傞傕偺偲尵偊傑偡丅抧壓奐敪棙梡尋媶僙儞僞乕偺妶摦偑崱屻偺抧壓棙梡偺傛傝堦憌偺敪揥偵婑梌偝傟傞偙偲傪婩擮偄偨偟傑偟偰丄擭摢偺垾嶢偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

仭儈僯僪乕儉娐嫬杊嵭憤崌幚尡仭
抧壓奐敪棙梡尋媶僙儞僞乕偑幚巤偟偰偄傞乽戝怺搙抧壓嬻娫奐敪媄弍乿偺尋媶奐敪偵偍偗傞丄僕僆僪乕儉偺僗僷僀儔儖揤斦峔憿岠壥傪幚徹偡傞偨傔偵暯惉俉擭俁寧偵姰惉偟偨儈僯僪乕儉偼俆寧枛偵姰惉幃傪峴偄丄偦偺屻奺庬偺娐嫬杊嵭幚尡傪儈僯僪乕儉撪偱峴偭偰偒偨丅偙傟傜偺掲傔偔偔傝偲偟偰丄崱夞懡悢偺嶲壛幰偺傕偲儈僯僪乕儉撪偱娐嫬杊嵭憤崌幚尡偑峴傢傟丄偁傢偣偰抧壓嬻娫棙梡偵偮偄偰偺島墘偍傛傃僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞偑峴傢傟偨丅
娐嫬杊嵭憤崌幚尡偼壒嬁偲捠婥丒娐嫬偵偮偄偰峴傢傟丄壒嬁幚尡偱偼丄僪乕儉撪摿桳偺巆嬁壒偑挿偄壒偲丄僪乕儉暻柺偵媧壒慬抲傪巤偟偰巆嬁壒傪捠忢偲摨偠偔傜偄抁偔偟偨壒偺俀庬椶偺壒傪棳偟丄壒偺姶偠曽傪傾儞働乕僩挷嵏偟偨丅傑偨丄摿庩側壒傪敪惗偝偣偰僪乕儉撪偵懡悢偺恖娫偑偄傞応崌偺壒嬁揱斃摿惈傕偁傢偣偰寁應偟偨丅
捠婥丒娐嫬幚尡偱偼捠婥偵傛傞姺婥岠壥傪攃埇偡傞偨傔丄嶲壛幰偑僪乕儉撪偵偄傞娫丄捠婥傪堦帪掆巭偟丄扽巁僈僗擹搙傗壏搙丄幖搙丄婥棳懍傪寁應偟偨丅傑偨丄嵟屻偵捠婥拞偵墝傪敪惗偝偣僪乕儉撪偺婥棳偺棳傟傪壜帇壔偡傞幚尡傪峴偭偨丅
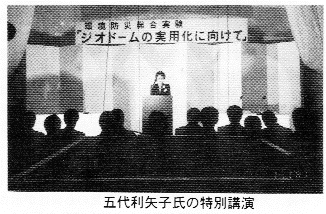 傑偨偙傟傜偺幚尡偲摨帪偵峴傢傟偨抧壓嬻娫偵娭偡傞島墘偍傛傃僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞偱偼丄偼偠傔偵昡榑壠偺屲戙棙栴巕巵傛傝乽抧壓偵偮偄偰巚偆偙偲乿偲戣偟偰摿暿島墘傪峴偭偰偄偨偩偄偨丅屲戙巵偼椪帪戝怺搙抧壓棙梡挷嵏夛偺儊儞僶乕偱偁傝丄偙傟傑偱朘傟偨抧壓巤愝側偳偺懱尡傪捠偟偰丄媄弍幰偲偼堘偭偨栚偱崱屻偺抧壓棙梡偺偁傝曽傪岅偭偰偄偨偩偄偨丅
傑偨偙傟傜偺幚尡偲摨帪偵峴傢傟偨抧壓嬻娫偵娭偡傞島墘偍傛傃僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞偱偼丄偼偠傔偵昡榑壠偺屲戙棙栴巕巵傛傝乽抧壓偵偮偄偰巚偆偙偲乿偲戣偟偰摿暿島墘傪峴偭偰偄偨偩偄偨丅屲戙巵偼椪帪戝怺搙抧壓棙梡挷嵏夛偺儊儞僶乕偱偁傝丄偙傟傑偱朘傟偨抧壓巤愝側偳偺懱尡傪捠偟偰丄媄弍幰偲偼堘偭偨栚偱崱屻偺抧壓棙梡偺偁傝曽傪岅偭偰偄偨偩偄偨丅
師偵乽僕僆僪乕儉偺幚梡壔偵岦偗偰乿偲戣偟偰係恖偺曽偵僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞傪峴偭偰偄偨偩偄偨丅彫搰孿擇嫵庼乮搶嫗戝妛乯傪僐乕僨傿僱乕僞乕偲偟偰俁恖偺僷僱儕僗僩丄姡丂晀堦巵乮捠彜嶻嬈徣丂嶻嬈巤愝壽丂壽挿乯丄愇嶈丂廏晲巵乮惔悈寶愝噴丂媄弍奐敪晹丂晹挿乯丄壴懞丂揘栫巵乮戝惉寶愝噴丂搚栘愝寁戞擇晹丂晹挿乯偑朄惂搙丄棙梡丄媄弍偺棫応偐傜敪尵偟丄拞恎偺擹偄媍榑偲側偭偨丅

仭夛堳偺奆條傊偺偍抦傜偣仭
仜擔婣傝尒妛夛偺偛埬撪
抧壓僙儞僞乕偱偼丄崱擭搙傕擔婣傝尒妛夛傪婇夋偄偨偟偰偍傝傑偡丅崱夞偼恄撧愳導曽柺偺壓婰偺抧壓巤愝俁偐強偺尒妛傪俀寧侾俉擔乮壩乯偵梊掕偟偰偄傑偡丅
| 嘆儈僯僪乕儉乮憡柾尨巗乯乧 |
崙撪桞堦偺戝怺搙抧壓嬻娫幚徹僪乕儉 |
| 嘇廰愳塉悈挋棷娗寶愝岺帠乮愳嶈巗乯乧 |
搒巗嵭奞懳嶔偲偟偰崙撪嵟戝媺偺戝岥宎丄
挿嫍棧偺戝怺搙塉悈挋棷巤愝 |
| 嘊傒側偲傒傜偄俀侾乮墶昹巗乯乧 |
怴偟偄抧壓搒巗偺抋惗丄
柉桳抧偺抧壓偵偼偠傔偰揝摴墂傕幚尰 |
徻偟偔偼嬤乆丄奺憢岥扴摉幰偵偛埬撪傪憲晅偄偨偟傑偡偺偱丄惀旕偙偺婡夛偵偛嶲壛偝傟傞傛偆偛埬撪怽偟忋偘傑偡丅乮恖悢偵尷傝偑偁傝傑偡乯

仭暯惉俉擭搙崙撪尒妛夛曬崘仭
抧壓奐敪棙梡尋媶僙儞僞乕偑椺擭幚巤偟偰偄傞崙撪尒妛夛偑丄崱擭傕侾侾寧侾俁擔乮悈乯乣侾俆擔乮嬥乯偵嶳岥愱柋棟帠傪抍挿偲偟偰丄憤惃係俁柤偺嶲壛偵傛傝峴傢傟偨丅崱夞偺僐乕僗偼嬤婨曽柺偱丄係偐強偺抧壓娭楢巤愝側偳傪帇嶡偟抦尒傪怺傔傞偲偲傕偵丄嶲壛幰憡屳偺恊杛傪怺傔傞偙偲偑偱偒丄桳堄媊側俁擔娫偲偡傞偙偲偑偱偒偨丅
戞侾擔栚丂戝嶃巗拞墰懱堢娰
 梡抧偺惂栺偲娐嫬曐岇偺栚揑偐傜抧壓偵寶抸偟偨懱堢娰偱丄柺愊栺俉丆侽侽侽噓偺侾枩恖廂梕偱偒傞儊僀儞傾儕乕僫傪偼偠傔僒僽傾儕乕僫丄廮寱摴応丄僩儗乕僯儞僌幒側偳偺巤愝偑愝偗傜傟偰偄傞丅抧忋偼幣惗傗庽栘側偳偺怉嵧偱暍傢傟偰彫崅偄媢偺岞墍偲偟偰偍傝丄偙偺暯嬒岤栺侾倣偺抧忋晹岞墍偺惙搚傗怉嵧摍傪巟帩偡傞偨傔丄儊僀儞傾儕乕僫偍傛傃僒僽傾儕乕僫偺壆崻偼悽奅偱傕嵟戝媺偺僾儗僗僩儗僗僩僐儞僋儕乕僩媴宍僔僃儖峔憿偲偟偰偄傞丅
梡抧偺惂栺偲娐嫬曐岇偺栚揑偐傜抧壓偵寶抸偟偨懱堢娰偱丄柺愊栺俉丆侽侽侽噓偺侾枩恖廂梕偱偒傞儊僀儞傾儕乕僫傪偼偠傔僒僽傾儕乕僫丄廮寱摴応丄僩儗乕僯儞僌幒側偳偺巤愝偑愝偗傜傟偰偄傞丅抧忋偼幣惗傗庽栘側偳偺怉嵧偱暍傢傟偰彫崅偄媢偺岞墍偲偟偰偍傝丄偙偺暯嬒岤栺侾倣偺抧忋晹岞墍偺惙搚傗怉嵧摍傪巟帩偡傞偨傔丄儊僀儞傾儕乕僫偍傛傃僒僽傾儕乕僫偺壆崻偼悽奅偱傕嵟戝媺偺僾儗僗僩儗僗僩僐儞僋儕乕僩媴宍僔僃儖峔憿偲偟偰偄傞丅
尒妛偼娰撪偺嵟怴愝旛偺夛媍幒偱俷俫俹傗價僨僆傪巊偭偰奣梫偺愢柧偑峴傢傟丄偙偺偁偲娰撪傪尒妛偟偨丅尒妛摉擔偼懱堢娰偺婡婍揰専擔偲偄偆偙偲偱丄傎偲傫偳偺巤愝偑巊梡偝傟偰偍傜偢丄棙梡幰偵婥寭偹偣偢偵偔傑側偔巤愝撪傪尒妛偡傞偙偲偑偱偒偨丅
戞俀擔栚丂惗栰峼嶳丄墱懡乆椙栘敪揹強憹愝岺帠
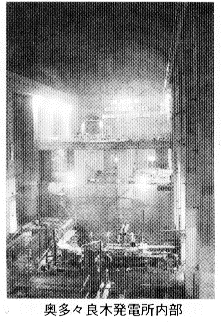 乲惗栰峼嶳乴
乲惗栰峼嶳乴
惗栰峼嶳偼戝摨俀擭乮俉侽俈擭乯偵奐岯偝傟丄幒挰擭娫偺揤暥侾侾擭乮侾俆係俀擭乯偵嶳柤桽朙偑嬧峼柆傪敪尒偟丄杮奿揑偼嵦孈偑巒傑偭偨丅埲屻柧帯偐傜徍榓偵偄偨傞傑偱崙撪桳悢偺戝峼嶳偲偟偰壱峴偟偰偒偨偑丄徍榓係俉擭偵暵嶳偟侾俀侽侽擭偺挿偄楌巎偵枊傪暵偠偨丅
尰嵼偼乽峼嶳岞墍惗栰嬧嶳乿偺柤偱岯摴偺堦晹傪堦斒偵奐曻偟丄傑偨晘抧撪偵帒椏娰丄峼暔娰傪愝抲偟丄惗栰嬧嶳偵娭偡傞帒椏傗崙撪偐傜峀偔廂廤偟偨峼暔昗杮傪揥帵偟偰偄傞丅岯摴偼巚偄偺奜挿偔丄尰戙偺嵦孈媄弍傗峕屗帪戙偺嵦孈曽朄傪恖宍側偳偱嵞尰偟偰偄傞偺傪挱傔偮偮丄栺俁侽暘傎偳偐偗偰岯摴撪傪堦廃偡傞傛偆偵側偭偰偄偨丅
乲墱懡乆椙栘敪揹強憹愝岺帠乴
暫屔導偺傎傏拞墰晹偐傜擔杮奀懁偵峀偑傞挬棃孮嶳偺扟娫偵埵抲偡傞梘悈敪揹強偱丄忋晹偲壓晹偺僟儉梕検偑戝偒偄偙偲偐傜丄婛愝敪揹強乮俈俀枩倠倂丗俁俇枩倠倂亊俀戜乯偐傜侾俀侽倣棧傟偨応強偵抧壓嬻摯傪峔抸偟丄憹愝敪揹強乮侾俀侾丏俀枩倠倂丗俁侽丏俁枩倠倂亊係戜乯傪寶愝偟偰偄傞丅
偼偠傔偵埬撪偝傟偨忋抮乮崟愳僟儉乯偱偼憹愝敪揹強梡偺庢悈岥偺庢傝晅偗偑峴傢傟偰偍傝丄偙偺岺帠偺忬嫷傪尒妛偡傞偙偲偑偱偒偨丅
師偵埬撪偝傟偨抧壓敪揹強撪晹偱偼嬻摯偺孈嶍偑廔椆偟丄敪揹婡悩偊晅偗偺偨傔偺婎慴岺帠偑峴傢傟偰偄偨丅嬻摯撪偼惍慠偲偟偰偄偰姺婥傕椙岲偱丄埨慡惈偵嵟戝偺攝椂傪偟側偑傜岺帠偑峴傢傟偰偄傞偺偑偆偐偑偊偨丅
戞俁擔栚丂嫗搒巗屼抮抧壓奨
偙偺抧壓奨偼嫗搒巗栶強慜偺屼抮捠傝偵偁傝丄偦偺廃曈偼楌巎揑寶憿暔偱偁傞巗挕幧傪偼偠傔屆偔偐傜偺挰壠偑尙傪楢偹傞側偳丄揱摑揑側忣弿偑巆偭偰偄傞丅偙偺偨傔抧壓俁奒偼抧壓揝墂丄抧壓俀奒偼挀幵応丄偦偟偰抧壓侾奒偵彜揦奨傪愝偗傞偙偲偱丄挰偺嬤戙壔傪恾傞偲偲傕偵丄抧忋偺楌巎揑側娐嫬傪庣傠偆偲偟偰偄傞丅
埬撪偝傟偨偆偪偱彜揦奨丄挀幵応偼偙傟偐傜愝旛娭學偺岺帠偵擖傠偆偲偟偰偄傞偲偙傠偩偭偨偑丄抧壓揝墂偼暯惉俋擭廐偵偼姰惉梊掕偲偄偆偙偲偱丄恀偭愒側儂乕儉僪傾乮僾儔僢僩儂乕儉懁偵庢傝晅偗傜傟偨幵椉忔崀梡偺僪傾乯偑晅愝偝傟偨儌僟儞側墂偑傎傏姰惉偵嬤偯偄偰偄偨丅
嵟屻偵崱夞偺尒妛夛偵偍偄偰丄偛嫤椡偄偨偩偒傑偟偨娭學幰偺曽乆偵夵傔偰偍楃傪怽偟忋偘傑偡丅
乮媄弍奐敪戞擇晹丂戝徖丂姲丂婰乯

仭戞侾俉俈夞僒儘儞丒僪丒僄僫奐嵜偺偍抦傜偣仭
壓婰梫椞偱丄戞侾俉俈夞僒儘儞丒僪丒僄僫傪奐嵜抳偟傑偡丅崱夞偼抧壓僙儞僞乕偺扴摉暘偲偟偰丄姅幃夛幮擔寶愝寁忢柋庢掲栶丂暯堜丂嬆丂巵傪偍寎偊偟丄抧壓搒巗偺僐儞僙僾僩傪傒側偲傒傜偄俀侾傪帠椺偲偟偨抧壓偺棫懱搒巗婡擻幚尰偵偍偄偰偺峔憿柺丄杊嵭柺丄朄惂搙柺丄娐嫬柺摍偱偺懡偔偺壽戣偲偦偺夝寛曽嶔偵偮偄偰偍榖偟捀偒傑偡偺偱丄懡悢偺偛嶲壛傪偍婅偄抳偟傑偡丅
| 侾丏擔丂帪丗 |
暯惉俋擭侾寧侾俇擔乮栘乯丂侾俈丗俁侽乣俀侽丗侽侽 |
| 俀丏応丂強丗 |
摉嫤夛俇奒俠俢俤夛媍幒丂
仹侾侽俆搶嫗搒峘嬫惣怴嫶侾亅係亅俇乮俠倄俢價儖乯 |
| 俁丏僥乕儅丗 |
乽抧壓偵棫懱搒巗婡擻偑幚尰偡傞乿
乣怴偟偄搒巗峔抸偵傛傞搚抧強桳懁丒棙梡懁丒帠嬈懁偺儊儕僢僩偺堦抳
乮傒側偲傒傜偄俀侾偺帠椺乯乣 |
| 係丏島丂巘丗 |
姅幃夛幮擔寶愝寁丂忢柋庢掲栶丂暯堜丂嬆丂巵 |
| 俆丏島墘梫巪丗 |
棫懱搒巗婡擻偑幚尰偡傞偨傔偵偼丄抧壓嬻娫棙梡偺壥偨偡栶妱偑戝偒偄丅侾俋俋俈擭偵姰惉梊掕偺僋僀乕儞僘僗僋僄傾乕墶昹偺僾儘僕僃僋僩傪徯夘偟丄棫懱揑側搒巗婡擻偑幚尰偟偨攚宨偵偮偄偰愢柧偡傞丅
乮侾乯俵俵俀侾抧嬫
乮俀乯僋僀乕儞僘僗僋僄傾乕墶昹乮俀係奨嬫乯
乮俁乯傒側偲傒傜偄俀侾慄乮抧壓揝摴乯
乮係乯僋僀乕儞僘僗僋僄傾乕墶昹偲傒側偲傒傜偄拞墰墂偺娭學
|
拲乯僒儘儞丒僪丒僄僫偼捠忢戞嶰悈梛擔偵奐嵜偟傑偡偑丄侾寧偺戞嶰悈梛擔乮侾俆擔乯偼嵳擔偵偁偨傞偨傔丄侾俇擔乮栘乯偺奐嵜偲側傝傑偡丅

|